障がい者射撃は、体の状態に合わせて誰でも挑戦できる精密スポーツです。集中力と安定した技術が鍵で、年齢や性別を問わず長く楽しめます。この記事では、競技の歴史やパラリンピックでの位置づけ、基本ルールをやさしく解説します。日本で始めるための手続きの流れまでカバーし、初心者の第一歩から経験者の精度向上まで役立つ内容をお届けします。
第1章:障がい者射撃とはどのような競技か
障がい者射撃は、パラリンピックでは1976年トロント大会で正式競技になりました。オリンピックの射撃は1896年アテネの第1回大会で実施され、その後一部の大会を除き継続して行われてきた歴史あるスポーツです。
競技は制限時間内に規定弾数を撃ち、その合計得点で順位を争います。使用する銃はライフルとピストルで、空気圧で弾を発射するエア銃と、火薬を用いる銃があります。
選手のクラス分けは、上肢で銃を自力保持できるかどうかが基準です。SH1(上肢で銃を保持できる)と、SH2(上肢では保持できず、支持スタンドを使う)の2クラスに分けられます。
車いす利用の有無に応じて姿勢や用具を調整し、安定して射撃できるよう規則が整えられています。
射撃は精密さに加えてメンタル面が極めて重要です。決勝は小数採点で行われ、決勝では0.1点刻み(最大10.9点)で評価されるため、わずかな差が勝敗を分けます。すべての発射で高得点を狙う集中力が求められます。
日本は2000年のシドニー大会でパラリンピック射撃に初参加して以降、2024年のパリ大会まで出場を重ねてきました。継続的な国際舞台での挑戦は、国内の選手育成や競技力向上にもつながっています。
射撃は年齢や性別を問わず取り組める点も特徴で、生涯スポーツとして楽しめます。若い世代から高齢者まで幅広い層が参加し、自分のペースで上達を目指せます。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 歴史 | パラリンピックでは1976年トロント大会から正式競技。オリンピックでは1896年アテネ大会で実施され、長い歴史を持つ。 |
| 競技内容 | 制限時間内に規定弾数を撃ち、その合計得点で順位を競う。ライフルとピストルを使用し、エア銃と火薬銃がある。 |
| クラス分け | 上肢で銃を保持できるかどうかで分類。SH1は自力保持可能、SH2は支持スタンドを使用。 |
| ルールの工夫 | 車いす利用の有無に応じて姿勢や用具を調整し、安定した射撃を可能にする規則が整備されている。 |
| 決勝の特徴 | 小数採点で0.1点刻み(最大10.9点)。わずかな差が勝敗を分け、極めて高い集中力が求められる。 |
| 日本の参加 | 2000年シドニー大会で初参加。2024年パリ大会まで出場を継続し、国内の育成や競技力向上に寄与。 |
| 生涯スポーツ | 年齢や性別を問わず楽しめ、若年層から高齢者まで幅広く参加可能。 |
第2章:射撃競技の姿勢とルール

パラリンピックの射撃競技では、「伏射(ふくしゃ)」「膝射(しっしゃ)」「立射(りっしゃ)」という3つの姿勢があります。それぞれ安定性や難易度が異なり、選手の技術や集中力が試されます。
伏射(ふくしゃ)
身体を床に伏せて撃つ方法で、最も安定した姿勢です。車いすの選手は、車いすに取り付けたテーブルを床の代わりにし、その上に両肘を置いて構えます。安定性が高いため、狙いを定めやすいのが特徴です。
膝射(しっしゃ)
しゃがんだ姿勢で撃つ方法で、銃を支える肘を膝の上にのせることで比較的安定します。車いすの選手は、片肘を置ける小さな台を「膝」に見立てて使用します。伏射に比べるとやや不安定ですが、集中力と体幹のバランスが重要になります。
立射(りっしゃ)
立ったまま銃を構える方法で、3つの中で最も不安定な姿勢です。車いすの選手は背もたれや脚に肘をあてることなく、両腕だけで銃を保持して撃ちます。体の支えが少ない分、腕の力や安定感が試されます。
競技の流れ
各姿勢の種目に出場する選手が一斉に並び、制限時間内に決められた弾数を撃ちます。その合計得点で順位が決まり、上位8名のみがファイナルに進出します。
ファイナルでは種目ごとにルールが異なりますが、点数の低い選手から順に脱落していき、最後まで高得点を出し続けた選手が優勝となります。緊張感の高いステージで、選手たちの集中力や精神力が試される瞬間です。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 伏射(ふくしゃ) | 身体を床に伏せて撃つ最も安定した姿勢。車いす選手は車いすに取り付けたテーブルに肘を置いて構える。狙いやすさが特徴。 |
| 膝射(しっしゃ) | しゃがんだ姿勢で肘を膝にのせて撃つ方法。車いす選手は小さな台を「膝」として使用。伏射より不安定で集中力と体幹のバランスが求められる。 |
| 立射(りっしゃ) | 立ったまま撃つ最も不安定な姿勢。車いす選手は肘を背もたれや脚にあてず、両腕のみで銃を保持。腕の力と安定感が試される。 |
| 競技の流れ | 各姿勢の選手が一斉に並び、制限時間内に規定弾数を撃ち合計得点で順位を決定。上位8名がファイナル進出。 |
| ファイナル | 点数の低い選手から順に脱落し、最後まで高得点を維持した選手が優勝。緊張感の中で集中力と精神力が試される。 |
第3章:銃の種類と特徴
ライフルやピストルには、火薬を使う「火薬銃」と、空気の圧力で弾を飛ばす「空気銃(エア銃)」の2種類があります。まずはライフルから紹介します。
火薬式のライフルは、直径5.6mmの鉛の弾を発射します。弾は先端が丸い形で、銃の重さはおよそ6〜7kgです。オリンピックやパラリンピックで使われるのは、音や反動が比較的小さいタイプの弾になります。
一方、エアライフルは直径4.5mmの鉛の弾を使用し、形は「鼓(つづみ)」のように先端が尖っていません。そのため空気抵抗の影響を考えながら撃つ必要があり、銃の重さは約5kgです。
どちらも選手の体格や姿勢に合わせて調整でき、上肢に障がいのある選手は補助スタンドを使うことができます。
ピストルにも同じく火薬銃と空気銃があります。火薬式は25m・50m種目で使われ、直径5.6mmの弾を撃ちます。重さは1kgほどで、通常のピストルより銃身が長く、手に合わせた特殊なグリップが特徴です。
空気式のピストル(エアピストル)は10m種目で使用され、直径4.5mmの鼓型の弾を発射します。重さは火薬銃と同じく約1kgです。
エア銃は反動がない分、弾が空気抵抗で減速しやすく、狙ったつもりでも弾がズレやすいため、繰り返し練習して感覚を掴むことが大切です。
火薬銃の場合は発射後に反動があり、撃った瞬間に銃が跳ね上がります。銃口が元の位置に戻れば「当たった」と感じられることもあります。命中率を高めるには「呼吸を整え、息をゆっくり吐きながら引き金を絞る」ことが大切です。
日本では空気銃を扱うにも警察の許可が必要で、練習場も限られているため競技人口は多くありません。しかし性別や年齢を問わず公平に競えるスポーツです。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| ライフル(火薬銃) | 直径5.6mmの鉛弾を発射。弾先は丸めで、銃重量は約6〜7kg。反動や発射音があるが競技用は比較的抑えられたタイプを使用。 |
| ライフル(エア銃) | 直径4.5mmの鉛弾(鼓形)を使用。弾は尖っておらず空気抵抗の影響を受けるため弾道の理解が重要。銃の重さは約5kg。 |
| 姿勢・用具の調整 | 選手の体格や姿勢に合わせて銃を細かく調整可能。上肢で保持できない選手は支持スタンド等の補助具を使用できる。 |
| ピストル(火薬銃) | 25m・50m種目で使用。直径5.6mm弾を発射。銃身が長く特殊グリップを備え、重さはおよそ1kg前後。 |
| ピストル(エアピストル) | 10m種目で使用、直径4.5mmの鼓型弾を発射。重さは火薬式ピストルと同程度で約1kg。 |
| エア銃の特性 | 反動がほとんどない反面、弾が空気抵抗で減速しやすく狙いどおりに飛ばすには繰り返しの練習で感覚を養う必要がある。 |
| 火薬銃の特性 | 発射時に反動があり銃が跳ねる。呼吸を整え、息をゆっくり吐きながら引き金を絞るなどのテクニックで命中率を高める。 |
| 練習と規制(日本) | 日本では空気銃でも所持に警察の許可が必要で練習場が限られるため競技人口は多くないが、年齢・性別問わず公平に競える競技である。 |
第4章:練習方法

練習では、呼吸のコントロールや引き金の引き方を少しずつ身につけていきます。発射時の反動や空気抵抗を体で感じながら精度を高めることが大切です。
指導者や仲間と一緒に取り組むことで、技術の向上だけでなく練習の継続やモチベーションの維持にもつながります。
また、自分に合った種目や姿勢を選んで練習すると効率的に上達できます。競技レベルに応じた練習方法を工夫したり、大会前に模擬試合を経験したりすることで、より実戦的な力を養うことができます。
射撃は技術だけでなく精神面も鍛えられるスポーツであり、集中力や冷静さが身につくことで、日常生活にも良い影響を与えると言われています。
第5章:日本国内での所持と参加の流れ
パラリンピックの射撃競技で使われる銃は、すべて鉛製の弾を発射する「実銃」です(※ビームライフルなど弾を使わない銃と区別するために「実銃」と呼ばれます)。
日本では銃を扱う際、必ず居住地の公安委員会から自分専用の銃の所持許可を受けなければなりません。他人の銃を借りて練習や大会に参加することはできず、必ず自分が所持する銃を使う必要があります。
銃の所持を始める第一歩は、居住地の警察署で実施される「猟銃等講習会(初心者講習)」を受講することです。講習会を受けるには、警察署の生活安全課で手続きを行います。講義の後に筆記試験があり、合格して初めて修了となります。
講習の開催頻度は地域によって異なり、2か月に1回のところもあれば半年に1回のところもあります。予定は都道府県警察のホームページで確認できるので、事前に調べておくことが大切です。
合格するには、申請時に配布されるテキストで予習し、当日の講義をしっかり聞いておくと安心です。初心者講習を修了した後、正式に「所持許可申請」を行います。
許可には年齢などの条件があり、日本の法律では「銃を自分で安全に管理・操作・保管できること」が必須条件です。
身体障害の有無は直接の条件ではありませんが、法律で定められた精神疾患や一定以上の認知機能障害がある場合は欠格事由となり、許可は得られません。最初に所持できるのは「空気銃(エアライフル、ハンドライフル)」です。
装薬ライフルやピストル(エアピストル・装薬ピストル)を持つには、まず空気銃やビームライフル/ピストルで実績を積み、所定の技量基準を満たしたうえで、日本スポーツ協会の推薦を受ける必要があります。
まとめ

障がい者射撃は、1976年からパラリンピック正式競技となった精密スポーツで、ライフルやピストルを用い制限時間内に得点を競います。選手は上肢の機能に応じてクラス分けされ、伏射・膝射・立射の姿勢で挑戦します。
日本で始めるには警察の許可が必要で、まず初心者講習を受講して空気銃の所持からスタートします。年齢や性別を問わず生涯楽しめ、集中力や精神力の向上にもつながる競技です。
あとがき
作者として障がい者射撃というスポーツがあることは、正直全く知りませんでした。銃を使うため、警察署での講習や所持許可が必要な事も初めて知りました。
それでも、集中力や精神力を鍛えながら楽しめる競技だと感じました。体験や観戦を通じて、新しい挑戦の面白さや達成感を味わえるスポーツだと思いました
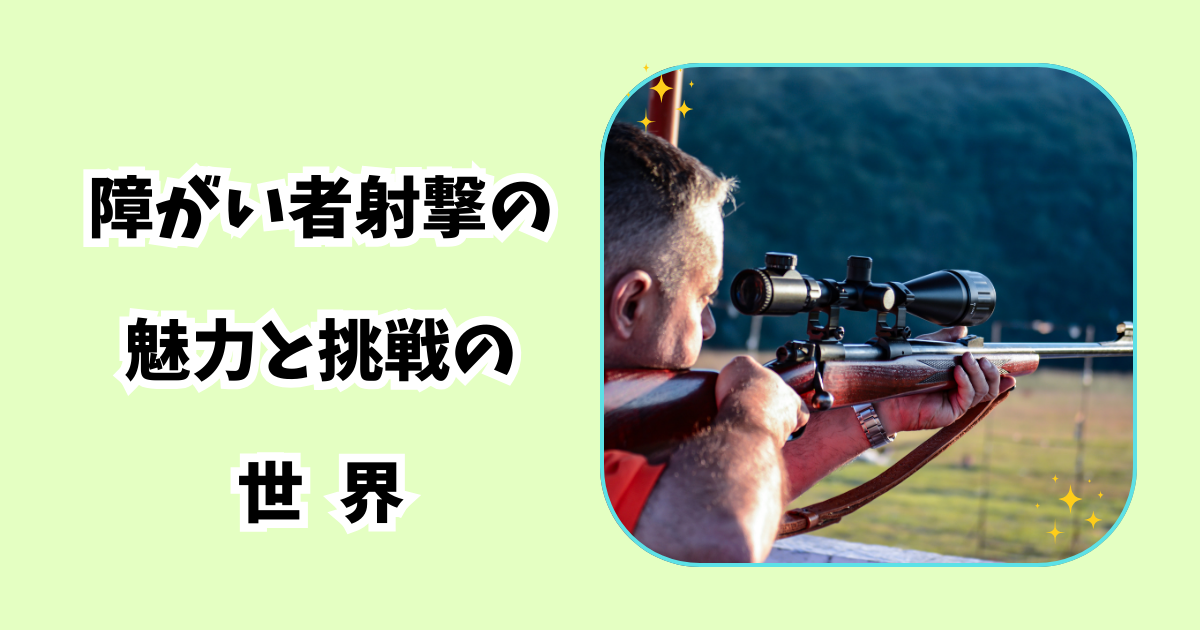
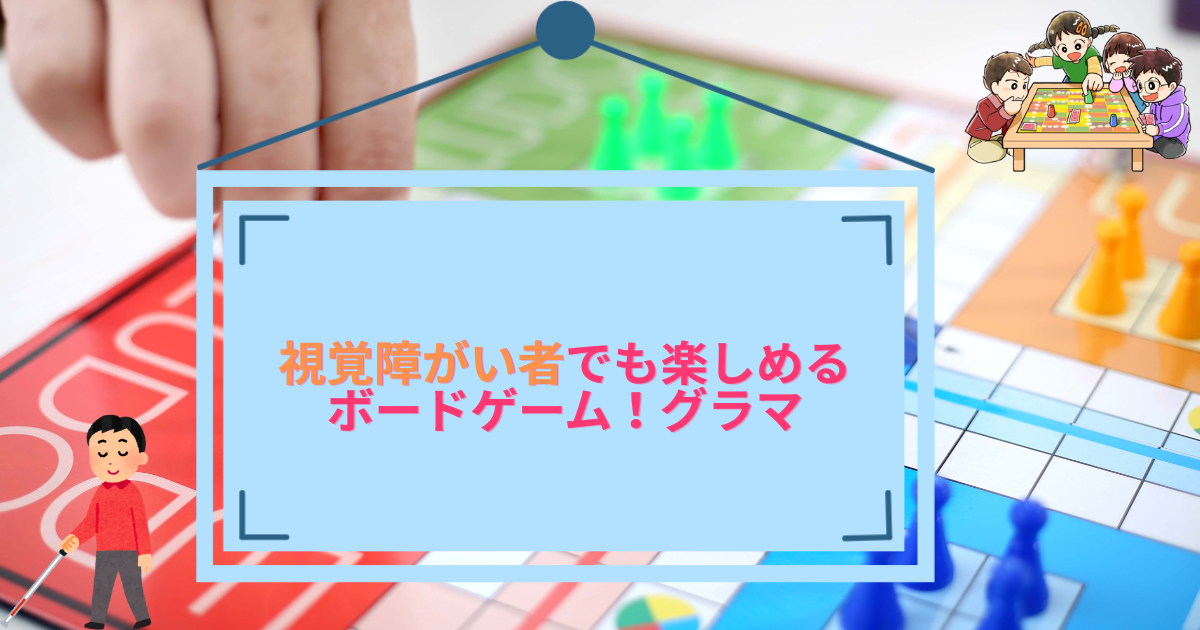

コメント