学校の先生や企業の社会貢献担当者、地域でボランティア活動をしている方で、障がいのある人たちと一緒に楽しめる活動を探していませんか?特に、スポーツを通じて多様な人々が交流する機会を創りたいと考えているかもしれません。しかし、具体的にどのような形で支援に関わればいいのか、情報が少なく困っている方もいるかもしれません。この記事では、視覚障がい者も一緒に楽しめるボードゲーム「グラマ」の魅力や、活用方法、支援の関わり方までご紹介します。
1. グラマとは?インクルーシブなボードゲームの魅力
グラマは、視覚の状態に関わらず誰もが一緒に楽しめる協力型のボードゲームです。基本は4人で、最初にそれぞればらばらの重さになるように準備した巾着袋を選びます。
プレイヤーは「コンビニにあるもの」「学校にあるもの」「緊張の重さ」などのテーマに合わせて、自分の袋の重さを言葉でたとえながら共有し、全員の袋の重さが揃うように重りを調整していきます。
最終判定では、4つの皿が付いた木製の天秤に全員の巾着袋を同時に載せ、釣り合えば成功、崩れて「ガシャン」という音が鳴れば失敗。アイマスクなどの特別な配慮や別ルールは不要です。
視覚に頼りきらずに、触覚(重さを感じる)と会話・聴覚(伝える・聞く)を活かして同じ条件で遊べるよう設計されています。
触覚と聴覚を活かしたユニークなルール
プレイの核心は「重さを感じて、言葉で伝える」こと。指先で袋の重さを確かめ、具体的なたとえで仲間に共有します。最後は天秤の静けさ(成功)や崩れる音(失敗)をみんなで同時に体験するため、見える・見えないに関わらず結果を共有できます。
振り返りでは、巾着の紐に付いた鈴の数で袋を識別し、互いの重さの感じ方の違いを確かめられる点も特徴です。
- 道具:巾着袋×4、重り、四皿の木製天秤
- 勝敗:勝ち負けではなく、全員で「成功/失敗」を共有
- 遊び方:重さをたとえで伝え合い、全員の袋の重さを揃える
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 基本情報 | 視覚の状態に関わらず楽しめる協力型ボードゲーム。基本は4人でプレイ。 |
| 準備 | それぞれ重さの異なる巾着袋を選び、テーマ(例:「コンビニにあるもの」「学校にあるもの」など)に沿って重さをたとえで共有。 |
| ルール | 全員の袋の重さが揃うように調整し、最後に木製天秤で判定。釣り合えば成功、崩れて「ガシャン」と鳴れば失敗。 |
| 特徴 | アイマスクや特別ルールは不要。触覚で重さを感じ、聴覚と会話で共有するユニバーサル設計。 |
| 振り返り | 巾着袋の紐に付いた鈴の数で袋を識別し、重さの感じ方の違いを確かめ合う。 |
| 道具 | 巾着袋×4、重り、四皿の木製天秤。 |
| 勝敗 | 勝ち負けではなく、全員で「成功/失敗」を共有。 |
| 遊び方 | 袋の重さを指先で確かめ、たとえを使って伝え合いながら調整し、全員の重さを揃える。 |
2. グラマがもたらす教育現場でのメリット

グラマは学校の授業や放課後活動など、教育の場での活用が期待されているボードゲームです。特にインクルーシブ教育が広がる中で、多様な生徒が一緒に学べるツールとして注目されています。
実際に学校現場での特別授業の導入事例もあり、視覚の状態にかかわらず全員で協力して遊べる点が評価されています。
コミュニケーション能力と協調性の向上
グラマでは、各プレイヤーが受け取った巾着袋の重さを、日用品や感情などのテーマにたとえて言葉で共有し、全員の袋の重さがそろうように調整します。
最終的に袋を四皿の天秤に載せ、釣り合えば成功となります。この過程で、相手の感じ方を想像して伝える力、聞き取ってすり合わせる力が育まれ、自然と協調性やチームワークの向上につながります。
ルールがシンプルなため、異なる背景の生徒同士が同じ目標に向かって取り組む良い機会になります。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 教育現場での活用 | 学校の授業や放課後活動などで導入が期待される。特別授業の事例もあり、インクルーシブ教育のツールとして注目。 |
| 評価点 | 視覚の状態にかかわらず、全員で協力して遊べる点が高く評価されている。 |
| プレイ方法 | 巾着袋の重さを日用品や感情などのテーマにたとえ、言葉で共有しながら全員の重さをそろえる。 |
| 判定方法 | 袋を四皿の天秤に載せ、釣り合えば成功。崩れれば失敗。 |
| 育まれる力 | 相手の感じ方を想像して伝える力、聞き取って調整する力が鍛えられ、協調性やチームワークの向上につながる。 |
| 特徴 | シンプルなルールにより、異なる背景を持つ生徒同士が共通の目標に向かって取り組める。 |
3. 企業や地域での活用事例と社会貢献の形
グラマは、企業や地域での社会貢献活動(CSR)にも活用できる可能性があります。
障がいの有無に関わらず一緒に楽しめるグラマは、ダイバーシティ&インクルージョンを推進する企業にとって、従業員同士の交流を深める効果的なツールとなるでしょう。
さらに、地域のお祭りやイベントで体験会を開催すれば、住民が障がい者支援に関心を持つきっかけにもなります。
インクルーシブなイベントの開催
企業のCSR活動として、グラマを使った体験会やワークショップを開催するのも良い方法です。従業員がボランティアとして参加し、地域の支援団体や学校と協力することで、より意義のある活動になるでしょう。
参加者からは「視覚障がいのある方と一緒にゲームをして新しい発見があった」「普段交流のない人と話せて楽しかった」といった感想が聞かれるかもしれません。
さらに、グラマは地域コミュニティの活性化にもつながります。年齢や障がいの有無に関わらず誰もが楽しめるイベントとして広がれば、人々が自然に集まり、交流できる場が生まれるでしょう。
グラマは、ただのゲームにとどまらず、人と人をつなぎ、社会のバリアを取り除く手段になり得るのです。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| CSRでの活用 | 障がいの有無を問わず楽しめるため、ダイバーシティ&インクルージョン推進の一環として従業員同士の交流を深められる。 |
| 地域イベント | お祭りやイベントで体験会を開催することで、住民が障がい者支援に関心を持つきっかけになる。 |
| インクルーシブな活動 | 企業CSRとしてワークショップや体験会を実施。従業員がボランティア参加し、地域団体や学校と協力することで意義が深まる。 |
| 参加者の声 | 「視覚障がいのある方とゲームをして新しい発見があった」「普段交流のない人と話せて楽しかった」などの感想が期待できる。 |
| 地域活性化 | 年齢や障がいの有無を超えて楽しめるイベントとして広がれば、自然な交流とコミュニティ形成が進む。 |
| 社会的意義 | グラマは、人と人をつなぎ、社会のバリアを取り除く手段としての役割を持つ。 |
4. グラマを始めるための具体的な方法

グラマに興味を持っても、「どこで手に入るの?」「どうやって体験できるの?」と思う方もいるでしょう。グラマは公式サイトや一部の専門店で購入することができます。
また、各地で体験会やワークショップも開かれている事もあり、実際に参加することでグラマの楽しさやインクルーシブな魅力を直接感じることができるでしょう。
ボランティアとして関わる方法
グラマを通じて社会貢献をしたい方には、ボランティアとして参加する方法があります。イベント運営を手伝ったり、プレイ方法をサポートしたりと、関わり方はさまざまです。
特別なスキルは必要なく、「一緒に楽しみたい」という気持ちがあれば誰でも参加できます。ボランティア活動を通じて障がいのある方と交流することで、その個性や能力、日常での工夫を理解できるきっかけになるでしょう。
こうした経験は、人生観や働き方に良い影響を与えてくれるかもしれません。まずはグラマの公式サイトやNPO法人の活動情報をチェックしてみてはいかがでしょうか。
5. グラマを通じて生まれる新しい可能性
グラマはただのボードゲームにとどまらず、新しい可能性を持っています。それは、障がいの有無に関わらず、互いを特別視せずに自然に交流できる「場」をつくり出すことです。
グラマという共通のツールがあることで、普段は出会う機会の少ない人々が集まり、遊びを通じて対等な関係を築くことができます。こうした体験は、インクルーシブな社会を実現するための小さな一歩になるでしょう。
グラマが広げる社会の輪
グラマを体験することで、「障がい」に対する見方が変わったと感じる人もいるでしょう。ゲームの中で視覚以外の感覚を駆使してプレイする姿は、「障がいがあるからできない」のではなく、「違う方法でならできる」という新しい発見につながります。
こうした気づきは、多様な人を受け入れ、誰もが活躍できる社会をつくる原動力になります。グラマの輪が広がれば、障がい者支援への関心が高まり、インクルーシブな活動も広がっていくでしょう。
それは障がいのある人だけでなく、私たち自身の視野を広げ、より豊かな社会を築くことにつながります。グラマは、人と人、人と社会をつなぐ希望のツールなのです。
まとめ

グラマは、視覚に障がいがある人もない人も一緒に楽しめる新しいボードゲームで、触覚や聴覚を活かす仕組みが大きな特徴です。教育現場では、生徒同士が互いの個性を尊重し合い、コミュニケーション能力や協調性を育むツールとして注目されています。
また、企業のCSR活動や地域イベントでも活用でき、従業員や住民が交流するきっかけとなります。さらに、ボランティアとして関わる方法もあり、誰でも気軽に参加できます。
グラマは、遊びを通じて障がいへの理解を深め、社会のバリアを取り除き、誰もが活躍できるインクルーシブな社会を実現するための希望のツールなのです。
あとがき
ここまで読んでくださりありがとうございます。記事作者が思ったことはグラマは、人と人をつなぐきっかけになる、素晴らしいツールだと感じます。ぜひ、一度体験してみてください。
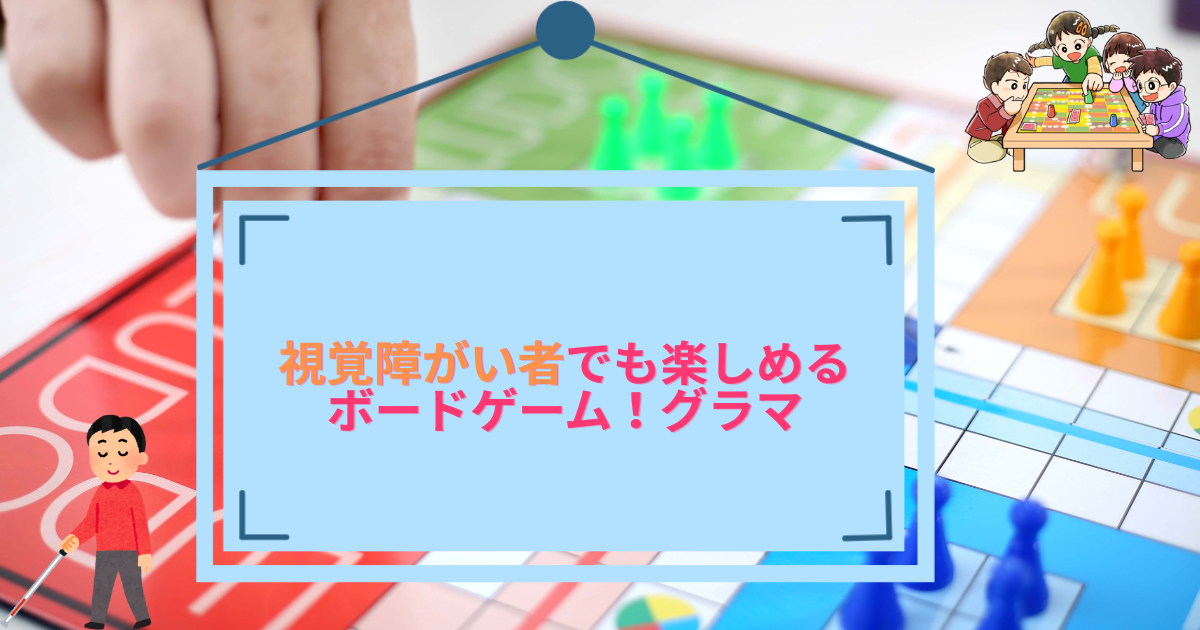
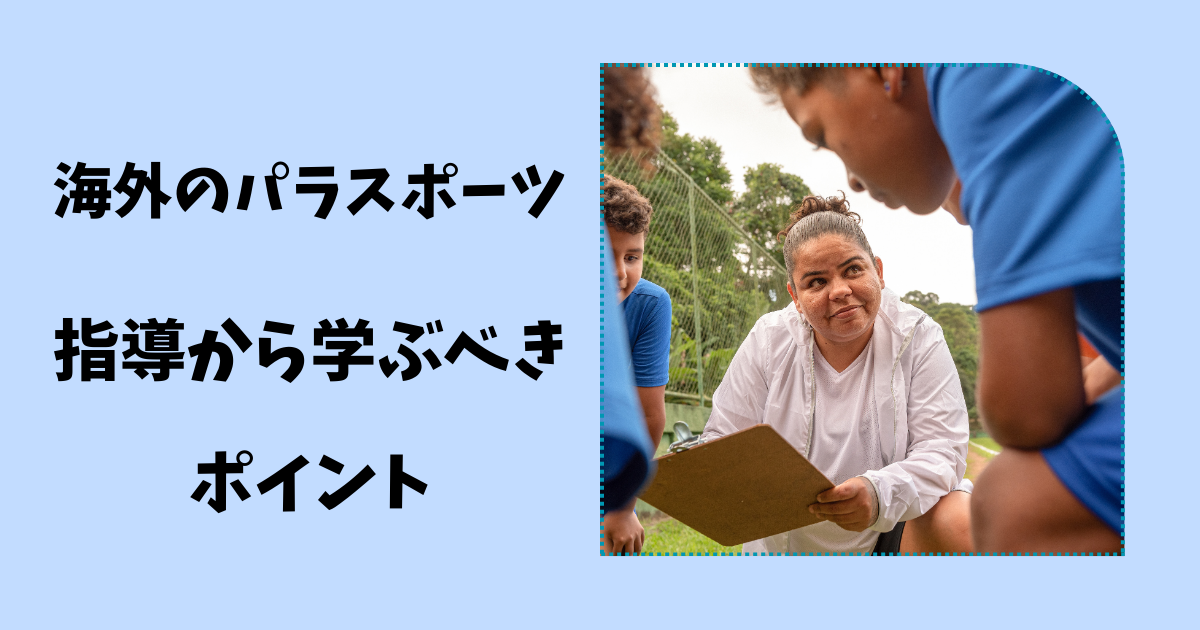
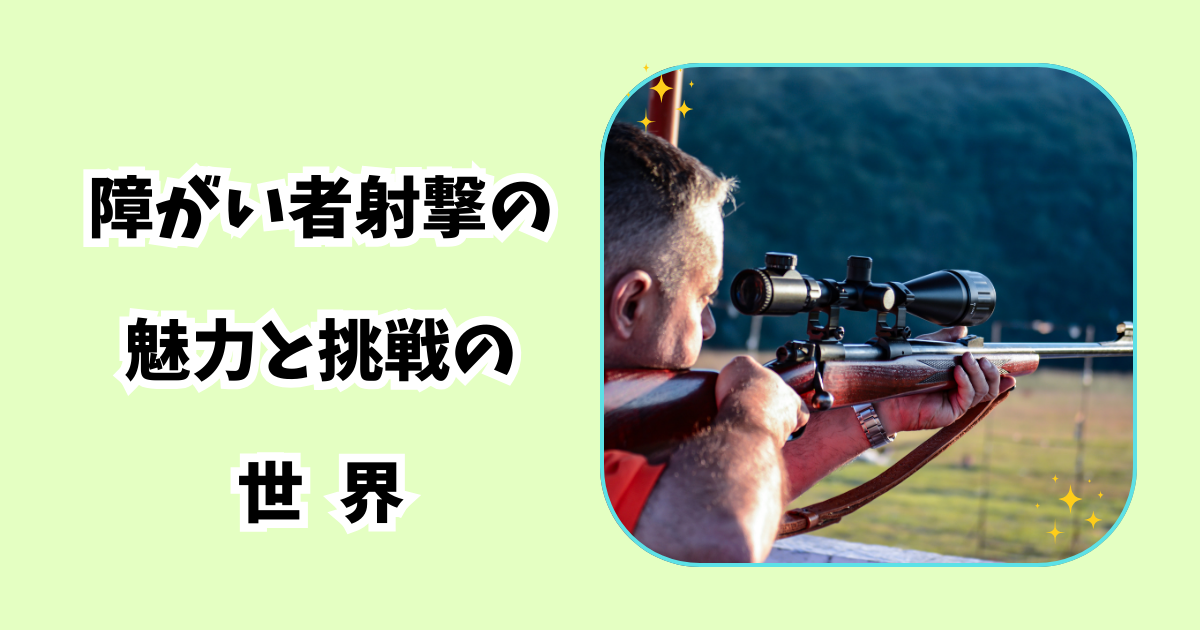
コメント