パラスポーツの魅力をもっと多くの人に届けたい――。そんな思いを実現するために、今あらためて広報戦略の見直しが求められています。そこで注目したいのが「KJ法」という思考ツール。この記事では、ロジカルに発想を整理し、斬新なPR戦略を導き出す方法について解説します。
第1章:パラスポーツの関心が高まる中での課題と可能性
東京2020パラリンピックは、パラスポーツの社会的な認知度を一気に高めるきっかけとなりました。選手たちの活躍や感動のシーンがテレビやSNSを通じて広まり、多くの人々が「パラスポーツってすごい」と感じたことでしょう。
しかしその一方で、イベント終了後の関心の持続には課題が残っています。一時的なブームで終わらせないためには、継続的な広報戦略が必要です。
偏りと断片化というPRのジレンマ
パラスポーツの広報には、いくつかの共通した悩みがあります。たとえば、「一部の人気競技や有名選手だけが注目される」「情報が断片的で、初心者にはとっつきにくい」などです。
これでは、せっかくの魅力や多様性が十分に伝わりません。広報の内容が一方向的だったり、視点が偏っていたりすることで、関心の裾野が広がりにくくなっているのです。
感動ではなく、共感と参加を生むPRへ
現代の広報において大切なのは、「すごい」と思わせるだけでなく、「私も応援したい」「観に行きたい」と感じてもらうことです。
そのためには、見る側の共感を引き出すストーリーや、関わりたくなるような導線設計が求められます。感動だけに頼る時代は、すでに過去のものとなりつつあります。
今こそ、新しい発想と仕組みが必要
こうした現状を打破するには、これまでの延長線上にない、まったく新しいPRの考え方が必要です。旧来型のイベント中心や紙媒体依存の戦略では、もはや限界があります。
だからこそ、今こそロジカルな発想と多様な視点を活かせる「思考の整理術」が力を発揮します。それが、後の章で紹介する「KJ法」です。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 東京2020の影響 | 東京2020パラリンピックは、選手の活躍や感動シーンがテレビやSNSを通じて広まり、社会的認知度を一気に高めるきっかけとなった。 |
| 課題:関心の持続 | イベント終了後の関心の継続に課題が残り、一時的なブームで終わらせないためには継続的な広報戦略が必要。 |
| PRのジレンマ | 人気競技や有名選手ばかりが注目され、情報が断片的で初心者にはわかりにくい。広報が一方向的で偏りがあり、多様性が十分に伝わらない。 |
| 共感と参加を生むPR | 「すごい」ではなく「応援したい」「観に行きたい」と感じてもらうことが重要。感動に頼るのではなく、共感を引き出すストーリーや参加を促す導線設計が求められる。 |
| 新しい発想と仕組みの必要性 | 旧来型のイベント中心や紙媒体依存の戦略では限界がある。今こそロジカルな発想と多様な視点を活かせる「思考の整理術」、つまりKJ法が有効。 |
第2章:パラスポーツPRの今までとこれから

パラスポーツの広報に関わる担当者は、実に多様な役割を担っています。SNSやWebサイトの更新はもちろん、イベント運営やメディア対応、そして社内外の調整業務まで携わることとなるのです。
その中で共通するのは、「どうすればパラスポーツの魅力をわかりやすく、効果的に伝えられるか」を常に考え続ける姿勢です。つまり、単なる情報の“発信者”ではなく、“価値を伝える編集者”としての意識が求められているのです。
情報の伝達から「対話」へと進化する広報
従来の広報は、発信者が一方的に情報を届ける「伝達型」が主流でした。しかし今はSNSやコメント機能を通じて、受け手との双方向コミュニケーションが可能な時代です。広報も単なる告知から脱却し、「会話」を通じてファンとの関係を築く姿勢が求められています。
共感される“価値”を見つけ出す力が重要
パラスポーツのPRで必要なのは、「注目を集める言葉」ではなく、「共感される価値」を見極める力です。
そこには、ただのコピーライティング以上に、深い観察力と構造的な思考が欠かせません。誰の心に響かせるか、どんな感情を動かすのか。その鍵を握るのが、次章でご紹介するロジカルシンキングの考え方です。
第3章:ロジカルシンキングが論理で発想を整理する強力な武器になる!
ロジカルシンキングとは、物事を筋道立てて整理し、因果関係や前提をもとに考える力のことです。複雑な問題をシンプルに分解したり、矛盾点を見つけて改善策を導き出す際にとても有効な思考法です。
「思いつき」から「戦略」へ変える考え方
広報やマーケティングの現場では、ふと浮かんだアイデアや感覚的な提案が出てくる場面が少なくありません。もちろん直感も大切ですが、それを形にして戦略として機能させるには、論理的に裏付けされた土台が必要です。
ロジカルシンキングを取り入れることで、「なんとなく良さそう」ではなく、「だから効果がある」という納得感あるPR戦略を作ることができるのです。
なぜパラスポーツPRに論理的思考が必要なのか
パラスポーツは競技の特性や対象者の多様性など、情報が複雑で専門的になりがちです。そのため、広報内容に一貫性を持たせたり、ターゲットごとに訴求点を整理したりする際に、論理的な視点が欠かせません。
どこに伝えるべき魅力があり、どう組み立てれば伝わるか。それを明確にするのが、ロジカルシンキングの力です。
感性と論理のバランスが成功のカギ
ただし、論理だけでは人の心は動きません。感動的なストーリーやビジュアルも重要な要素です。大切なのは、「感性で惹きつけ、論理で納得させる」というバランスです。
論理をもとにした企画設計に、感性で磨いた表現を掛け合わせることで、より深く心に届く広報が実現します。その橋渡しをしてくれるのが、次章で紹介する「KJ法」なのです。
第4章:KJ法とは?~アイデアを生み出す技法~

KJ法は、文化人類学者・川喜田二郎氏が開発した思考整理の技法です。たくさんの情報や意見があふれて収拾がつかないときに、それらを「見える化」しながら意味を発見していく手法として知られています。
特に、正解がひとつに決まらない問題や、複雑な課題に対して新たな切り口を見つけ出すのに力を発揮します。
手順:カード化 → グルーピング → ラベリング → 構造化
KJ法の手順はシンプルですが、奥深いものです。まずはアイデアや情報を一枚ずつのカード(または付箋)に書き出します。次に、それらを似た内容でグルーピングし、まとまりに名前(ラベル)をつけていきます。
さらに、それらのグループ同士の関係性を考えながら、全体の構造を図解していくことで、新たな気づきや方向性が浮かび上がってくるのです。
見える化による気づきの効果
KJ法の大きなメリットは、「頭の中だけで考えていたこと」が視覚的に整理されることです。
情報が見える形になることで、抜けや重複、矛盾が自然と明らかになります。また、複数人で行えば、お互いの認識のズレも共有でき、チームとしての方向性をそろえる助けにもなります。
なぜ広報戦略にKJ法が有効なのか?
パラスポーツのPRには、選手の魅力、競技特性、社会的メッセージなど多くの要素が関係します。それらを整理し、的確な訴求軸を定めるにはKJ法が非常に有効です。
単なるアイデアの羅列ではなく、構造的に意味づけされることで、戦略としての説得力が生まれます。多様な視点を尊重しながら合意形成できる点も、チームで広報を担う現場にぴったりです。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| KJ法とは | 文化人類学者・川喜田二郎氏が開発した思考整理の技法。多くの情報や意見を「見える化」しながら意味を発見する手法として知られている。 |
| 効果を発揮する場面 | 正解がひとつに決まらない問題や複雑な課題に対して、新しい切り口を見つけ出すのに有効。 |
| 手順 | ①カード化 → ②グルーピング → ③ラベリング → ④構造化。情報をカードに書き出し、グループ化し、ラベルを付け、構造化して図解することで新たな気づきを得られる。 |
| 見える化による効果 | 頭の中の考えを視覚化することで、抜けや重複、矛盾が自然と明らかになる。複数人で行えば認識のズレを共有でき、チームとしての方向性を揃えやすくなる。 |
| 広報戦略での有効性 | パラスポーツPRの要素(選手の魅力、競技特性、社会的メッセージなど)を整理し、訴求軸を定めるのに有効。構造的に意味づけされることで説得力が高まり、多様な視点を尊重しつつ合意形成できる。 |
第5章:KJ法を使ってパラスポーツPRを考える。ワーク形式で解説
KJ法を用いたパラスポーツPR考案に関して、具体的な手順を見ていきましょう。
ステップ1:情報を集める
KJ法の第一歩は「情報を集める」ことから始まります。ここではパラスポーツに関する幅広い素材を収集していきます。
たとえば、各競技のルールや見どころ、選手のインタビューや背景、イベント現場での観客の反応、SNSでの口コミなど、現場とメディアの両方から多面的な情報を集めることがポイントです。
ステップ2:カードにしてグループ化する
次に集めた情報を、1項目ずつカードや付箋に書き出していきます。それを見ながら、意味が近いものや同じ視点を持つもの同士でグループ分けしていきます。
たとえば「共感」「課題」「魅力」など、自然とカテゴリーが浮かび上がってくるはずです。この段階では正解を求めず、自由な発想でグループ化することが大切です。
ステップ3:グループに名前をつける
カードの束ができたら、それぞれにラベルをつけて意味づけを行います。これは「このグループは何を象徴しているか?」という問いへの答えでもあります。
ラベルをつけることで、情報の集まりが「単なるメモ」から「伝えるべき価値ある要素」へと変わっていきます。ここでのキーワードが、今後のPR企画の軸になります。
ステップ4:広報戦略の仮説を立てる
グループに名前をつけたら、いよいよ広報の全体像を設計していきます。たとえば、どんなストーリーで伝えるか、どのメディアを使うか、誰に届けるかという“仮説”を立ててみましょう。
重要なのは、ここで生まれた仮説をもとに、チーム内で意見を出し合いながらブラッシュアップしていくプロセスです。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| ステップ1 情報を集める |
パラスポーツに関する幅広い素材を収集する。競技のルールや見どころ、選手インタビュー、観客の反応、SNSの口コミなど、多方面から情報を集める。 |
| ステップ2 カードにしてグループ化する |
収集した情報を1項目ごとにカードや付箋に書き出し、意味が近いもの同士でグループ化する。「共感」「課題」「魅力」など自然にカテゴリーが浮かび上がる。 |
| ステップ3 グループに名前をつける |
グループにラベルを付けて意味づけする。情報が単なるメモから「価値ある要素」に変わり、今後のPR企画の軸となるキーワードになる。 |
| ステップ4 広報戦略の仮説を立てる |
どんなストーリーで伝えるか、どのメディアを使うか、誰に届けるかといった広報戦略の仮説を立てる。チーム内で意見を出し合い、ブラッシュアップして完成度を高める。 |
第6章:KJ法で生まれるきっかけに発想が社会を動かす
KJ法は、パラスポーツの広報において「共感と行動」を生み出すための有効な思考ツールと言えます。
利用者視点に立った情報整理により、伝えるべき価値やストーリーが浮かび上がり、日常のリアルな場面を切り取るような新しいPRアイデアも生まれます。チームで実践することによって多様な視点が融合し、説得力ある戦略が構築できるでしょう。
感動だけでなく、見る人が「関わりたくなる」広報へと進化させるには、発想力と整理力の両方が求められます。その両輪を育てるKJ法は今後の広報担当者にとって不可欠な武器になるでしょう。
まとめ

パラスポーツの広報には、感動を伝えるだけでなく、共感や参加を促す“戦略的な発想”が求められています。KJ法は、複雑で断片的な情報を整理し、新しいPRの切り口を見つけるための強力なツールです。
チームで活用すれば、多様な意見を束ねながら、利用者視点に立ったアイデアが生まれやすくなります。ロジカルシンキングとKJ法を武器に、これからの広報担当者は“伝える力”を超えて、“つながる力”を育てていきましょう。
あとがき
KJ法の使いどころは、本文中で述べてきた分野に留まりません。構想を練る場面においては様々な方面で使えます。実際、このAI生成記事について、どんな内容にするか主旨を見出す際にも KJ法が用いられているのです。
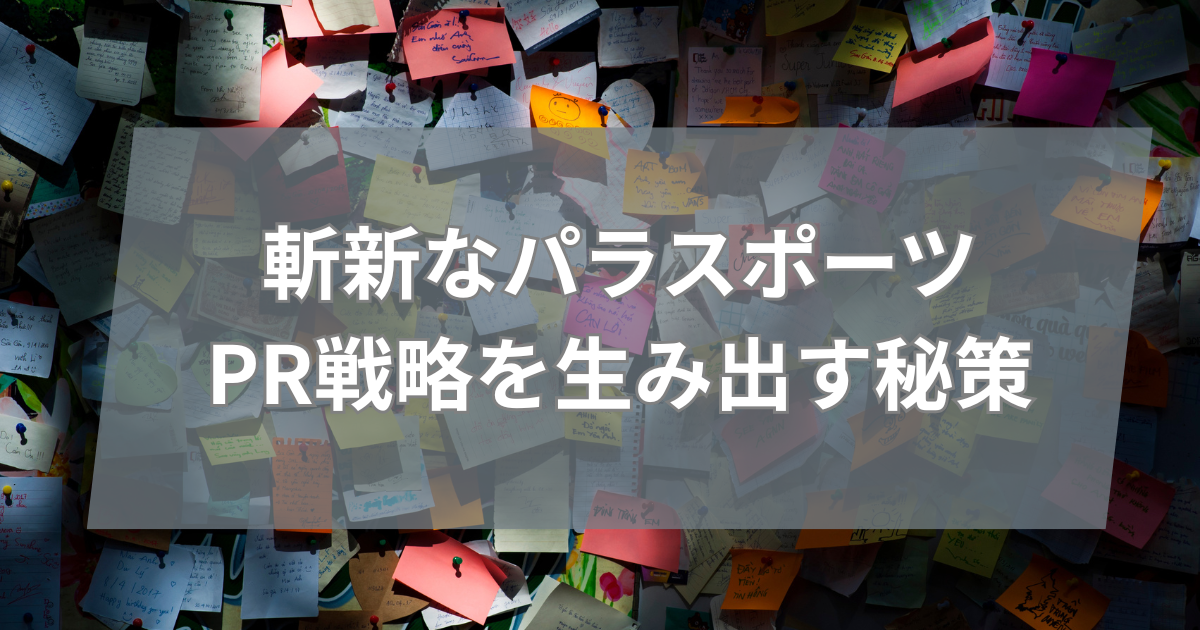
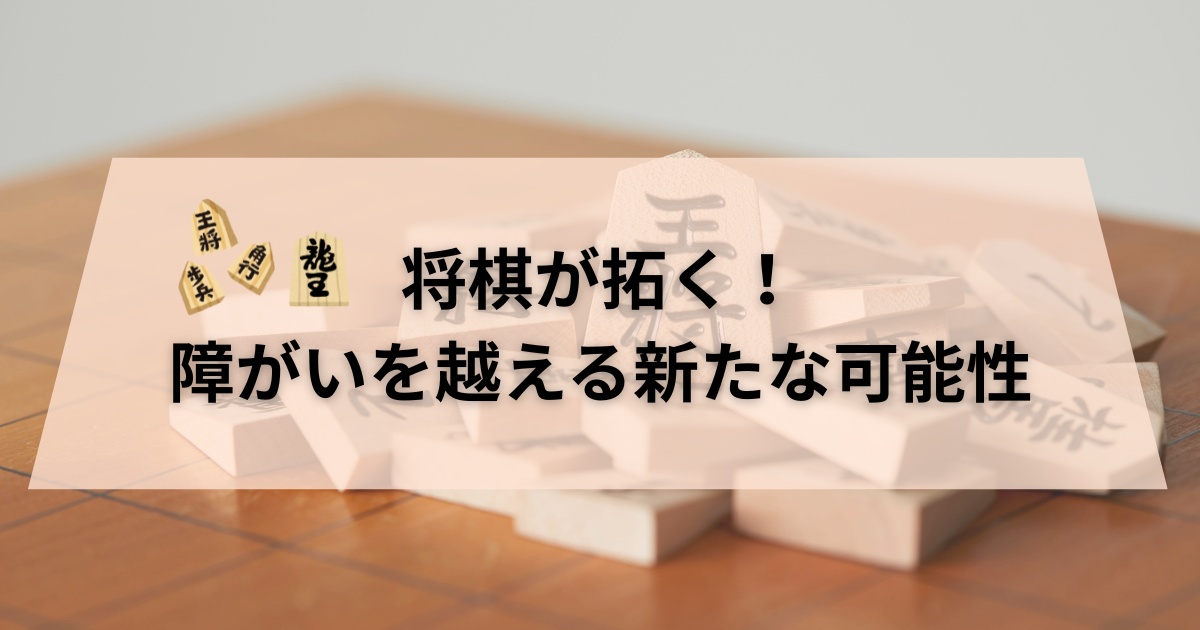

コメント