CPサッカーは、脳性まひなどによる運動機能の障がいがある選手たちがプレーする7人制サッカーです。競技としての魅力だけでなく、社会的な意義や感動のストーリーにも注目が集まっています。この記事では、CPサッカーの魅力と関わり方を紹介します。
CPサッカーとは?──脳性まひ者7人制サッカーの基本ルール
CPサッカー(Cerebral Palsy Football)は、脳性まひや脳卒中、脳外傷などにより四肢に運動機能の障がいがある人を対象とした7人制サッカーです。一般的なサッカーのルールをベースとしつつ、障がいの特性に配慮した独自の規定が設けられています。
たとえば、ピッチサイズは通常のサッカーより小さく、ゴールのサイズも縮小されています。また、オフサイドのルールは採用されておらず、スローインは片手で行っても反則とはなりません。
選手は障がいの程度に応じて「FT1」から「FT3」に分類され、チーム編成では重度障がいの選手(FT1)を常に1人以上出場させることが義務づけられています。これにより、異なる障がいレベルの選手が公平にプレーできる環境が確保されています。
試合は30分ハーフで行われ、7人制ながら戦術やスピードに富んだ試合展開が特徴とされています。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 競技概要 | CPサッカー(Cerebral Palsy Football)は、脳性まひ・脳卒中・脳外傷などにより四肢に運動機能障がいがある人を対象とした7人制サッカー。 |
| ルールの特徴 | 一般的なサッカーをベースに、障がいの特性に配慮した独自規定を採用。ピッチとゴールは小さく、オフサイドなし、スローインは片手でも可。 |
| クラス分け | 選手は障がいの程度に応じて「FT1」から「FT3」に分類される。 |
| チーム編成 | 重度障がいの選手(FT1)を常に1人以上出場させることが義務づけられ、公平なプレー環境を確保。 |
| 試合形式 | 試合は30分ハーフで行われ、7人制ながら戦術性とスピード感に富んだ展開が特徴。 |
国際大会とパラリンピックでの位置づけ
CPサッカーは1984年のニューヨーク・ストークマンデビルパラリンピックで初めて公式種目となり、2016年リオデジャネイロ大会まで継続して採用されました。しかし、2020年の東京パラリンピックでは競技種目から外されました。
国際大会としてはIFCPF(国際脳性まひサッカー連盟)が主催するワールドカップや地域別選手権などが開催されており、競技レベルは高い水準を維持しています。
ワールドランキングや国際大会の成績は、IFCPFの公式サイトを通じて随時公開されており、競技の国際的な広がりや選手たちの実力を確認することが可能です。
CPサッカーが再びパラリンピック種目として復活するかどうかは未定ですが、国際的な関心は一定数存在しており、関係団体による継続的なロビー活動も行われています。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| パラリンピックでの採用 | 1984年ニューヨーク・ストークマンデビル大会で初めて公式種目となり、2016年リオ大会まで継続採用されたが、2020年東京大会では外された。 |
| 国際大会 | IFCPF(国際脳性まひサッカー連盟)が主催するワールドカップや地域別選手権が開催され、高い競技レベルを維持している。 |
| ランキング・成績 | ワールドランキングや国際大会の成績はIFCPF公式サイトで随時公開され、競技の国際的広がりや選手の実力を確認できる。 |
| 今後の展望 | CPサッカーが再びパラリンピック種目として復活するかは未定だが、国際的関心は存在し、関係団体によるロビー活動も継続している。 |
日本代表の歩みと現在の挑戦
日本におけるCPサッカーは、2000年代以降に徐々に認知が進み、現在では日本CPサッカー協会が代表チームの強化や普及活動を担っています。日本代表は過去にアジア・オセアニア地域選手権などに出場し、各国と競い合ってきました。
代表選手の多くは、仕事や学業と競技を両立しながら、限られた時間の中で練習に励んでいます。トレーニング環境はまだ十分とは言えませんが、地域クラブや支援団体と連携しながら選手育成の取り組みが進められています。
直近では2023年のIFCPFアジア・オセアニア選手権に出場するなど、国際大会への継続的な参加が行われており、2026年の世界大会を視野に入れた強化体制が構築されています。メディア露出が限られている中、SNSなどを活用して情報発信にも取り組んでいます。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 普及と運営 | 2000年代以降に認知が進み、日本CPサッカー協会が代表チームの強化や普及活動を担っている。 |
| 国際大会参加 | 日本代表はアジア・オセアニア地域選手権などに出場し、各国代表と競い合ってきた。 |
| 選手の環境 | 代表選手の多くは仕事や学業と競技を両立し、限られた時間で練習に励んでいる。トレーニング環境は十分ではないが、地域クラブや支援団体と連携して育成が進められている。 |
| 直近の活動 | 2023年のIFCPFアジア・オセアニア選手権に出場。2026年の世界大会を見据えた強化体制が構築されている。 |
| 情報発信 | メディア露出が限られているため、SNSなどを活用した情報発信に取り組んでいる。 |
CPサッカーの観戦の魅力と注目ポイント

CPサッカーは、戦術の柔軟性とスピード感のある展開が観戦の魅力です。オフサイドが存在しないため、攻撃の選択肢が広がり、ダイナミックなプレーが頻繁に見られます。
また、障がいの程度が異なる選手たちが協力し合いながらゲームを組み立てる姿も、観戦の大きな見どころとなっています。
プレー中には、味方のフォローや相手へのリスペクトが自然と表現されており、スポーツマンシップにあふれる試合展開が多く見られます。
観戦初心者でも理解しやすいルール構成であることもあり、家族連れや学生など幅広い層に向けたスポーツイベントとしても親しまれつつあります。
日本国内での普及活動と地域クラブの取り組み
CPサッカーの普及に向けた取り組みは、東京・神奈川・埼玉などの都市圏を中心に、地域クラブによる活動としても展開されています。日本CPサッカー協会は、全国各地で研修会を実施しており、参加者の中から新たな競技者が育つこともあります。
こうした地道な活動の積み重ねにより、競技の認知度は徐々に高まりつつありますが、地方ではまだ情報が行き届かない地域もあり、継続的な発信が課題とされています。
障がい者スポーツとしての社会的意義
CPサッカーは単なるスポーツ競技という枠にとどまらず、リハビリテーションや社会参加の一環としても重要な役割を果たしています。
また、チームスポーツであることから、仲間との協力やコミュニケーション能力の向上にもつながっており、自己肯定感を高める機会にもなっています。
さらに、競技活動を通じて社会とつながり、目標を持って取り組むことができる点でも、参加者にとって大きな意義があります。
共生社会の実現に向けた取り組みとして、CPサッカーは教育現場や福祉施設でも注目されており、今後もその社会的役割は広がっていくと考えられています。
CPサッカーを支える人たち──指導者・スタッフ・家族
CPサッカーの現場では、選手だけでなく、多くの支援者の存在が欠かせません。
競技面では、選手一人ひとりの障がい特性を理解したうえでトレーニングを指導するコーチや、リハビリテーションの視点から身体のケアを担当する理学療法士、トレーナーの役割が重要です。
さらに、競技の継続には家族の理解と支援が大きな支えとなっています。日々の練習への送り迎えや生活面でのサポート、精神的な励ましなど、家族の関わり方は多岐にわたります。
また、競技団体を支える運営スタッフやボランティアの存在も不可欠で、試合の準備、用具の管理、広報活動など、さまざまな役割を担っています。こうした多様な支援が重なり合うことで、選手たちが安心して競技に集中できる環境が築かれています。
ボランティアや応援で関わるには?

CPサッカーに関心を持った人が関わる方法はさまざまです。CPサッカーのチームによってはボランティアの募集が行われており、特別な知識がなくても参加できる内容が多く見られます。
また、SNSでの情報発信や拡散、選手やチームへの寄付、会場での観戦も立派な応援の形です。情報が限られている障がい者スポーツの現場においては、応援の方法を知ること自体が支援への第一歩となります。
日本CPサッカー協会の公式サイトや各地域クラブのSNSアカウントなどでは、最新情報やイベント案内が発信されているため、まずはそうした情報源をフォローすることから始めてみるのもよいでしょう。
これからの展望──次世代への継承と国際舞台への挑戦
CPサッカーの日本代表は、将来的な国際大会出場や競技レベルの向上に向けて、選手の育成に力を入れています。また、2026年のIFCPFワールドカップなど国際舞台での活躍を目指した強化活動も行われています。
今後は、教育現場での普及や地域大会の開催、企業や自治体との連携を通じて、CPサッカーの価値がさらに広まっていくことが期待されています。競技だけでなく、社会への波及効果にも注目が集まっています。
挑戦を力に変える──あるCPサッカー選手の歩みから
CPサッカーの現場には、障がいと向き合いながら競技に打ち込む選手たちのリアルな姿があります。ある日本代表選手の歩みは、その象徴とも言えるものです。
先天性の脳性まひを持って生まれた彼は、周囲から障がいについて知らされず育ち、成長の過程で「自分はなぜ周りと違うのか」と悩みながら思春期を迎えました。
しかし、あるきっかけでCPサッカーと出会い、自らの障がいを受け入れる契機となったそうです。初めて出場した国際大会では、他国選手の技術と体力に圧倒され、大きな悔しさを味わったと語られています。
それでも、「自分にもできるはず」と信じ、高いレベルの環境を求めて地道に練習を重ねました。健常者のチームにも積極的に参加し、サッカーと真剣に向き合う中で、自分の身体への理解や自信も深まっていったといいます。
現在は世界選手権を目指して日々鍛錬を続けるとともに、障がいのある子どもたちが自らの可能性に挑戦できる環境づくりにも関心を寄せています。
CPサッカーを通じて、誰もが前向きに生きることの価値を感じられる社会を目指す姿は、多くの人に勇気と希望を与える一例と言えるでしょう。
まとめ

CPサッカーは、競技としての面白さだけでなく、選手一人ひとりの挑戦と支援する人々の存在によって成り立つ、深い人間ドラマを内包したスポーツです。障がいのある選手がチームプレーを通じて自己表現を行い、社会とのつながりを実感する場でもあります。
CPサッカーが今後さらに社会に根付き、多様性を尊重する文化の一部として成長していくことが期待されています。
あとがき
CPサッカーについて調査を進める中で、競技の奥深さだけでなく、選手たちの真摯な姿勢と、それを支える周囲の存在に強く心を動かされました。
障がいがあるからこそ生まれる工夫や努力、それを共有しながらプレーする仲間たちの姿は、スポーツの本質を思い出させてくれます。
まだまだ一般には知られていない側面も多い競技ですが、知ること・伝えることが支援の一歩になると感じています。この記事がCPサッカーへの理解と関心を深める一助になれば幸いです。


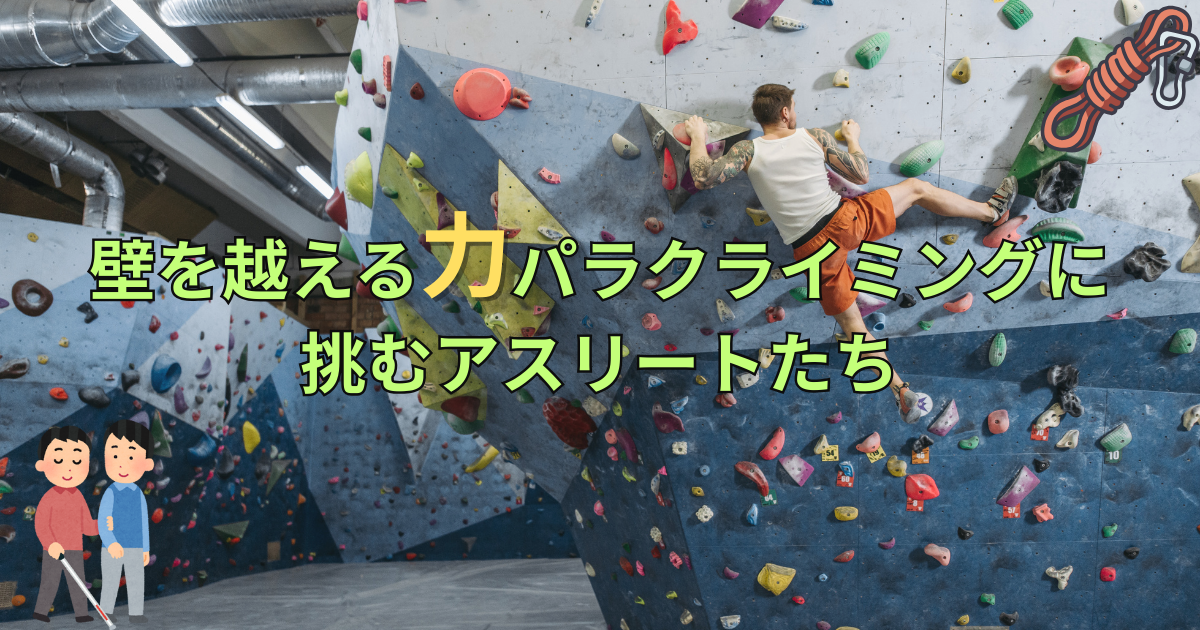
コメント