「柔道って、相手の動きを見るからこそ戦えるスポーツじゃないの?」と思う方も多いかもしれません。けれど、視覚障がい者柔道の世界では、目に頼らず、相手の気配や体重の移動、わずかな呼吸の変化さえも感じ取りながら闘いが繰り広げられています。 この記事では、見えないからこそ強くなる選手たちの驚きの技術や工夫、そして観戦の楽しみ方について紹介します。
1. 視覚障がい者柔道とは?
視覚障がい者柔道は、視覚に障がいのある選手が行うパラスポーツの一種で、正式には視覚障がい者柔道と呼ばれています。基本的なルールや技の種類は一般の柔道と同じですが、大きな違いのひとつが組んだ状態から試合が始まるという点です。
通常の柔道では、試合開始の合図と同時に選手が距離を測りながら組み合うのに対し、視覚障がい者柔道では、互いの道着をしっかりと掴んだ組み手の状態からスタートします。
これは、視覚による情報が得られない選手にとって、相手の位置や動きを手の感覚でとらえるための重要な工夫です。審判が選手の位置を調整し、両者がバランスよく組んだ状態ではじめの合図が出されます。
また、試合中に選手同士が離れてしまった場合は、審判が待てをかけて再び組んだ状態から再開されます。このようなルールは、選手同士が常に接触していることで安全性を保ち、同時に技をかけるチャンスを公平に確保するために設けられています。
以前は、視覚障がいの程度(全盲・弱視など)に関係なく、すべての選手が同じカテゴリーで競技していました。しかし見える選手と見えない選手が戦うのは本当に公平なのか?という議論を経て、2022年からは視力の程度によるクラス分けが導入されました。
現在では、選手は全盲(J1)と弱視(J2)に分類され、それぞれのクラスで競技が行われます。これは、より公平な試合環境を実現するための重要な改革です。
視覚障がい者柔道は、感覚を研ぎ澄まし、相手の力を見極める感知の格闘技として、見る者にも深い感動と驚きを与えてくれます。
2. 驚くべき技術と感覚の世界

視覚障がい者柔道では、視覚以外の感覚を最大限に研ぎ澄ませて戦う、まさに感覚の格闘技とも言える世界が広がっています。選手たちは相手の呼吸や衣擦れの音、畳のきしみといった微細な聴覚情報を頼りに、相手の動きやタイミングを読み取ります。
これは、まるで音を聴いて投げるかのような試合運びであり、健常者の柔道とはまた違った緊張感と高度な技術が要求される競技です。
また、手や腕を通じて伝わるわずかな力の変化、体重移動や重心のズレといった触覚的な情報も非常に重要です。組み手の状態で常に接触しているため、選手同士の間合いは常にゼロに近くなります。
そこでは、呼吸のリズムや体のわずかな揺れも戦術の手がかりになるのです。相手のちょっとした力の抜き方や反応速度まで感じ取り、瞬時に技を仕掛ける反射力が求められます。まさに感覚のぶつかり合いと言える接戦が繰り広げられます。
視覚障がい者柔道の観戦者にとってのポイントは常に組み合った状態で展開される組み手の攻防や間合いの変化、技が決まる瞬間の動きに注目することです。また、場内に響く選手の足音や息遣い、そして技が決まった時の落下音まで、すべてが試合の一部として体感できます。
視覚に頼らないからこそ、試合には独特の静けさと緊張感が漂い、音や気配に敏感になることで、より深く競技の本質を感じ取ることができるのです。集中力と感性の極限に挑むこの競技は、観る人の心にも強く響きます。
3. 注目選手の紹介

廣瀬順子(ひろせ じゅんこ)選手は、2023年のIBSA柔道グランプリ東京大会・女子57kg級で銅メダルを獲得した実力派の視覚障がい者柔道選手です。
小学校5年生で柔道を始め、中学・高校・大学と競技を続けてきました。19歳のときに膠原病を発症して半年間入院し、その合併症により視覚に障害が残りましたが、諦めることなく視覚障がい者柔道へ転向し、国際舞台でも活躍しています。
廣瀬選手は2016年のリオデジャネイロ・パラリンピックで銅メダル獲得、さらに2021年東京パラリンピックにも出場し、日本代表として実力を発揮しました。結婚後は、同じく視覚障がい者柔道の元選手で現在はコーチである夫・廣瀬悠氏と二人三脚でトレーニングに取り組んでいます。
最近では2024年のIBSA柔道グランプリ・アンタルヤ大会では女子57kg級(J2)で優勝を果たし、2024年パリパラリンピック(J2)女子57kg級でも優勝を果たしています。堅実な組み手と粘り強さを武器に、安定した試合運びで国際大会でも存在感を示す、今後の活躍がさらに期待される選手です。
藤本聰(ふじもと さとし)選手は、視覚障がい者柔道界のレジェンドと称される存在です。徳島県出身、左目の弱視(国内ではJ2)ながら、1996年アトランタ、2000年シドニー、2004年アテネと3大会連続金メダルを獲得しています。
北京では銀、リオでは銅メダルに輝いており、その実績はまさに競技人生の頂点といえるでしょう。現在は徳島視覚支援学校で教員として後進を育成し、地域・学校の支援のもと、継続して指導者として貢献しています。
瀬戸勇次郎(せと ゆうじろう)選手は、福岡県出身、73kg級のパラ柔道精鋭として知られています。東京2020パラリンピック柔道66kg級で銅メダルを獲得し、続くパリでは73kg級へ階級変更しながら金メダルを獲得した、若きパワーの象徴です。
視力は矯正しても0.1未満でありながら、福岡出身で4歳で柔道を始め、「心の眼」で相手に挑む精神性を強く持っています。現在は筑波大学大学院を無事に修了し、2025年春からは地元・糸島高校で教員として新たな歩みを始める瀬戸勇次郎選手です。
これら3選手に共通するのは、本人たちの日頃の努力に加えて、家族や伴走・指導者の献身的なサポートがあってこその成功です。
このように、廣瀬、藤本、瀬戸の三選手は、それぞれ異なる背景とキャリアを持ちながらも、「競技と人生を通じた自己成長」「家族・社会との連携」「後進への還元」という共通のテーマを胸に、日本の視覚障がい者柔道界を牽引しているのです。
彼らの挑戦と歩みは、観る者に大きな勇気と希望を届け続ける存在と言えるでしょう。
4. 観戦はできる?
競技観戦については国内外の大会に注目が集まっています。2025年5月にカザフスタン・アスタナで開催されたIBSA柔道世界選手権は視覚障がい者柔道の国際大会として注目されました。
国内では毎年全日本視覚障害者柔道選手権大会が開催され、時には東京・講道館で実施されることもあります。観戦の際は、視覚障がい者柔道特有の「組み合って開始するルール」を理解し、静かに選手の声や審判・アナウンスに耳を傾けることがポイントです。
選手の呼吸や動きの変化を感じながら観戦することで、より深く試合の流れを楽しめます。観戦後はSNSなどで選手への感想や応援メッセージを発信すると、競技の認知を広げる一助になります。
5. まとめ

視覚障がい者柔道は、「できない」ではなく「どう工夫するか」という視点を教えてくれるスポーツです。
多様な身体や感覚を持つ選手の挑戦は、私たちにも新たな気づきを与えてくれます。まずは観戦することから、誰でもパラスポーツ支援の一歩を踏み出せます。
6. あとがき
私も「できない」ことが多いと感じる日があります。でも視覚障がい者柔道の世界を知り、「工夫する力」が人を強くすることに気づきました。この記事が、あなたの視点を少しでも変えるきっかけになれば嬉しいです。

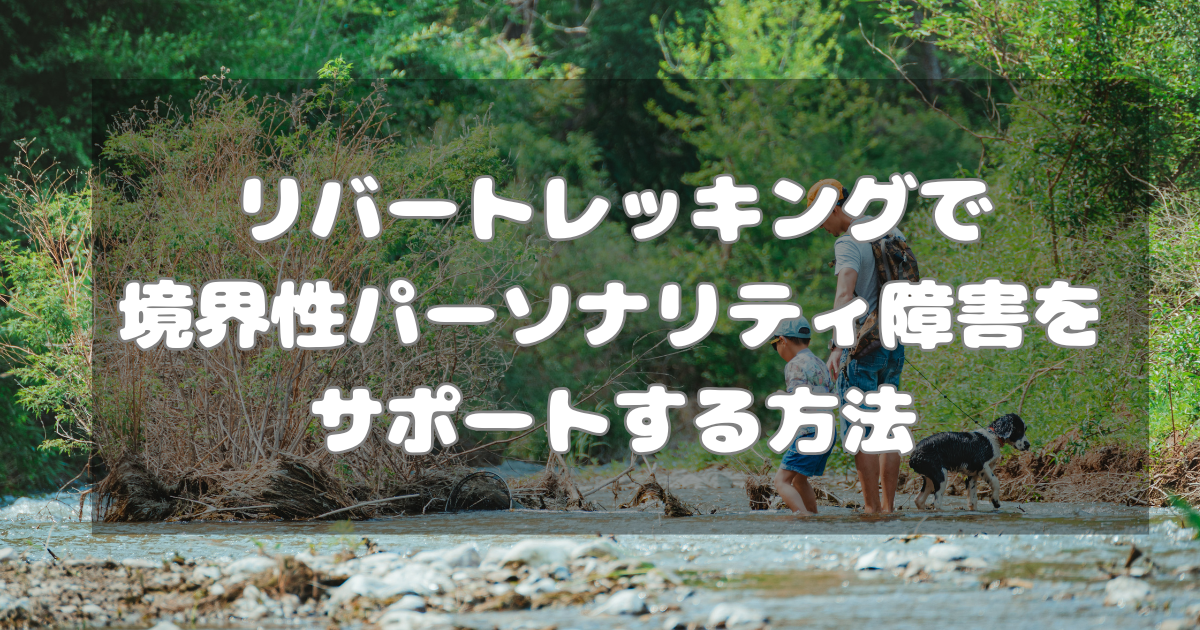

コメント