ウォーキングフットボールは、走らず歩いてプレーすることで安全性を高めた新しいスタイルのサッカーで、年齢や性別、障がいの有無にかかわらず誰もが参加しやすいことが特徴です。日本でも普及活動が進み、パラスポーツやリハビリ運動の一環としての活用例も見られます。この記事では、その魅力や健康効果、国際大会の様子、そして地域での広がりについて紹介します。
ウォーキングフットボールの誕生と世界的な広がり
ウォーキングフットボールは、2011年にイギリスで考案された新しいスポーツで、サッカーのルールをベースにしながらも「走らない」という特徴を持っています。
この競技は、高齢者の健康維持や運動不足解消を目的に発展してきましたが、現在では年齢や性別、障がいの有無にかかわらず幅広い層が楽しめるスポーツとして国際的に広がっています。
国際ウォーキングフットボール連盟(FIWFA)には多数の国が加盟しています。日本でも近年注目され、国際大会への参加や国内カップの設立など、普及活動が本格化しています。
誰でも参加できる!年齢・経験を問わない魅力

ウォーキングフットボールの最大の魅力は、その間口の広さにあります。走ることが禁止されているため、サッカーのような激しい運動が苦手な人や、体力に自信のない人でも参加しやすくなっています。
サッカー経験者でなくても、数分のルール説明で試合に加われる点は新規参加者にとって大きな利点です。プレーは全員が同じペースで行うため、世代や性別、運動経験の差がプレーの障壁になりにくい構造です。
また、障がいを持つ方やリハビリ中の方も、安全性を確保したルールの中で一緒にプレーできるため、インクルーシブなスポーツとしての性格を強く持っています。
スポーツを通じた交流は単なる運動以上の価値を生み、チームワークや相互理解を育むきっかけとなります。多様なバックグラウンドを持つ人々が同じフィールドで笑顔を交わす光景は、この競技の本質的な魅力のひとつです。
日本で定着するための普及活動と団体の取り組み
日本では、JFA(日本サッカー協会)などの団体が中心となり、普及活動が進められています。これらの団体は、全国各地で体験会やルール講習会を開催し、初心者や高齢者でも安心して参加できる場を提供しています。
普及活動の一環として、体験会や学校での授業導入も試みられています。国際大会出場を目指す選手育成と並行して、地域密着型の活動を行うことで、幅広い層への浸透を図っている点が特徴です。
ルールと安全性への工夫
ウォーキングフットボールは、安全性を高めるためにいくつかの独自ルールが設けられています。代表的なものとしては、走らず歩くことを徹底するルールがあります。また、接触は禁止され、身体をぶつけたり強く押したりするプレーは反則となります。
ヘディングは原則禁止で、ボールの高さも制限され、地上から一定の高さ(ゴール高さ)を超えるプレーは認められません。
日本独自のルールとしては、相手が保持しているボールを取らないことが定められています。これらの工夫により、接触や転倒による怪我のリスクを抑え、安全かつフェアな環境が保たれています。
健康効果──有酸素運動と脳の活性化を同時に実現
ウォーキングフットボールは、歩きながらボールを操作するという動作が継続的な有酸素運動となり、心肺機能や下半身の筋力維持に役立ちます。
走らないとはいえ、方向転換やパス、シュートの動作は多くの筋肉を使うため、通常のウォーキングよりも消費カロリーが高くなります。また、試合中は常に周囲を観察し、瞬時に判断してプレーを選択する必要があるため、脳への刺激も豊富です。
このような要素は認知機能の維持や反応速度の向上にもつながる可能性があります。さらに、複数人でのプレーは自然な会話や声掛けを促し、社会的交流を活性化します。
定期的に参加することで、運動習慣の定着やストレス軽減、生活の質の向上が期待できる点も期待されています。
障がいの有無を超えて楽しめるインクルーシブなスポーツ
ウォーキングフットボールは、年齢や性別だけでなく、障がいの有無に関係なく参加できるスポーツとして注目されています。競技ルールが接触や走行を禁止しているため、身体機能に制限がある方でも比較的安全にプレーできる環境が整っています。
実際に、義足を使用する方や軽度の運動制限がある方が健常者と同じフィールドでプレーする事例も見られます。
このような取り組みは、スポーツを通して互いの立場や状況を理解し合う「共生社会」の実践につながります。こうしたインクルーシブな特性は、スポーツファンだけでなく、地域活動や教育分野でも高く評価されています。
国際大会と日本代表チームの活動
国際ウォーキングフットボール連盟(FIWFA)が主催するワールドカップや国際親善試合では、各国の代表チームが集まり、年齢や経験を超えた熱戦が繰り広げられます。
大会は単なる競技の場にとどまらず、選手同士やスタッフ間の文化交流の機会にもなっています。特に、パラリンピックや障がい者スポーツに関心を持つ層からは、こうした国際舞台での活動が多様性理解や応援のきっかけとして注目されています。
また、帰国後は国内で報告会や体験会を行い、国際経験を地域に還元する取り組みも続けられています。
体験会・講習会から始めるウォーキングフットボール

ウォーキングフットボールは、全国各地で初心者向け体験会やイベントが行われています。体験会では基本ルールや安全なプレー方法の説明があり、経験者がサポート役として参加し、新規参加者が安心して楽しめる雰囲気づくりに努めていることでしょう。
また、障がいのある方や高齢者向けに、ペースを落とした練習や特別ルールを導入する可能性もあります。講習会では審判や指導者の育成も行われ、普及活動の担い手を増やすことが目指されています。
こうしたイベントは地域のスポーツセンターや公共施設などで開催され、参加者同士の交流や地域活性化にもつながっています。初めての方でも気軽に始められる点は、このスポーツの大きな魅力です。
これからの地域コミュニティにおける可能性
ウォーキングフットボールは、地域コミュニティにおいて健康促進と交流促進を同時に実現できるスポーツとして期待されています。少人数から始められ、広いフィールドや特別な設備を必要としないため、自治体や地域団体が取り入れやすいのが特徴です。
地域イベントや健康フェスティバルでの体験会は、世代を超えた交流のきっかけとなり、特に高齢者の孤立防止や若者とのコミュニケーション促進に役立つ可能性があります。
さらに、障がい者スポーツやパラリンピック競技との親和性も高く、共生社会の啓発活動の一環としても位置づけられます。継続的に実施することで、地域住民が顔見知りとなり、防災や互助の基盤づくりにもつながると考えられています。
こうした多面的な効果は、単なるレクリエーションを超え、地域資源としての価値を高めています。
まとめ

ウォーキングフットボールは、走らず歩いてプレーするというシンプルなルールを軸に、年齢や性別、障がいの有無を問わず楽しめるスポーツとして世界的に広がりを見せています。
ウォーキングフットボールは、競技としてだけでなく、健康増進や地域づくりの一環としても大きな可能性を持つ活動といえるでしょう。
筆者あとがき
今回の記事を通して、ウォーキングフットボールが持つ幅広い魅力と可能性についてあらためて考える機会となりました。
調査を重ねる中で、単なる「ゆるいサッカー」ではなく、健康維持、地域交流、そして多様な人々のつながりを生み出す力を秘めたスポーツであることを実感しました。
特に、世代や立場を越えて同じフィールドに立ち、笑顔でボールを追う姿はとても印象的でした。
この記事が、読者の方がウォーキングフットボールを知り、体験してみようと思うきっかけになれば嬉しく思います。もし近くで体験会や大会を見かけたら、まずは気軽に足を運び、その雰囲気を味わってみてください。
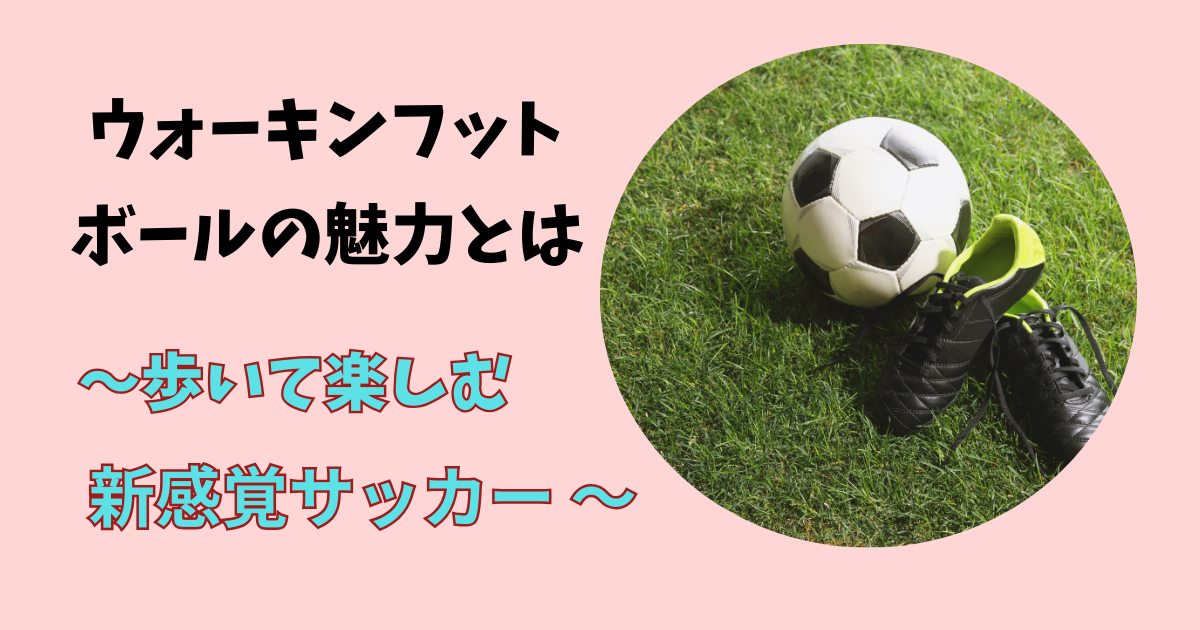

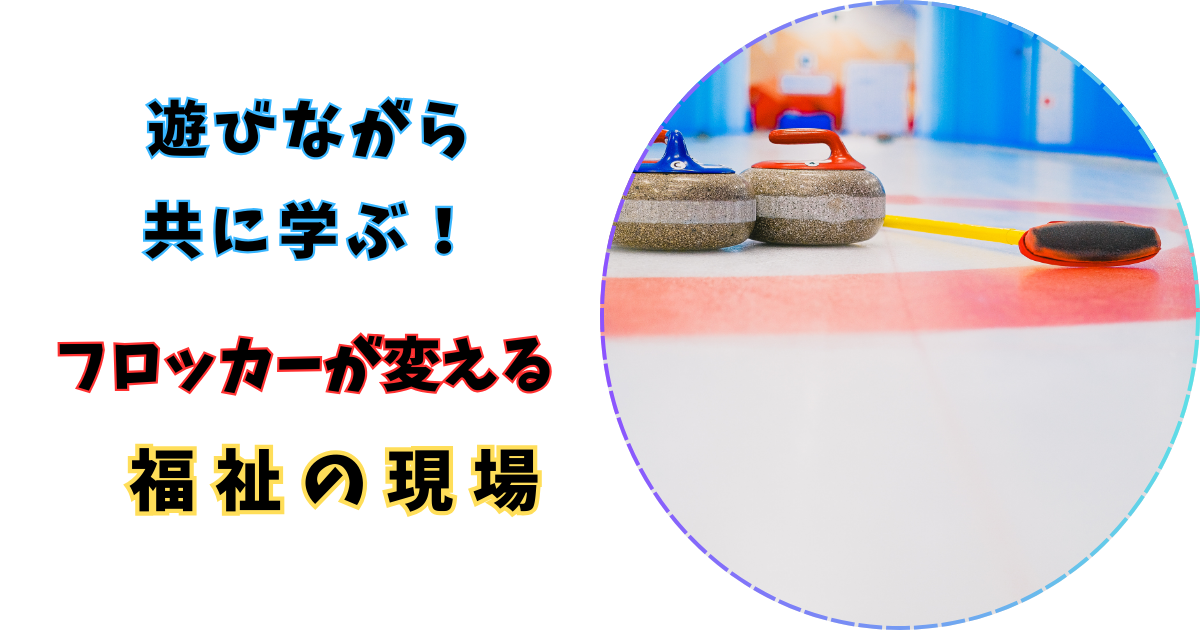
コメント