「運動が苦手で、すぐ転んでしまう」「ボールを投げても全然うまくいかない」──そんな悩みを抱えるお子さんはいませんか?その背景に、発達性運動協調障害(DCD)という発達の特性が関係していることがあります。DCDはまだ広く知られていませんが、運動のつまずきが「できない気持ち」につながることもあります。しかし、関わり方や工夫次第で少しずつ自信を育てることも可能です。この記事では、DCDの基本と、おすすめのスポーツや運動を紹介します。
1. 発達性運動協調障害(DCD)とは?
発達性運動協調障害(DCD)は、「協調運動」と呼ばれる体の動きを調整する脳機能がうまく働かない発達障害の一つです。
「協調運動」とは、目で見た情報や触れた感覚、自分の体の動きの感覚などを脳がまとめて「どう動くか」を計画し、実行する脳の一連の働きのことです。この機能が弱いと、体の動きがぎこちなくなりバランスを崩しやすくなります。
日常生活の中で、思うように体が動かせないことが繰り返されるため、本人も周囲も困難を感じやすくなります。DCDの子どもは、頭では「こうしたい」と思っても、体がうまく動かせず、縄跳びやキャッチボールのタイミングがつかめなかったりします。
苦手なのは体育だけでなく、「靴ひもを結ぶ」「お箸を使う」「字を書く」など、日常の細かい動作も難しく感じることが多いです。こうした細かい動きがうまくいかないことは、学校生活や家庭生活での困りごとにつながることもあります。
この不器用さは「やる気がない」「練習が足りない」と誤解されることもあり、子どもの自信を奪ってしまう原因になることがあります。本人の努力では解決しにくい特性であることを理解することが大切です。
DCDは、注意欠如・多動症(ADHD)や自閉症スペクトラム障害(ASD)と併存することも多く、単なる「不器用な子」として見過ごされやすい特徴があります。
しかし、苦手の背景にある脳の働き方を正しく理解し、適切な支援や環境づくりを行うことで、子どもが安心して成長できる土台を作ることができます。まずは「なぜ運動が苦手なのか?」を知ることが、支援の第一歩となるのです。
2. なぜDCDの子は運動でつまずきやすいのか

1章で説明したように、DCDでは脳の「協調運動」の機能に課題がありますが、ここでは特に、体の感覚情報の処理が難しい点に注目します。
体の位置や動きを感じ取る「固有受容覚」や、バランスを調整する「前庭感覚」がうまく働かないと、体の動きを正確に把握したり調整したりすることが困難になります。そのため、動きのタイミングや強さをうまくコントロールできず、ぎこちない動作になってしまうのです。
また、こうした感覚のズレは子どもにとって大きなストレスの原因となります。うまく動けないことで自己肯定感が低下し、「自分は運動が苦手だ」という気持ちが強まることも少なくありません。
さらに、集団の中で動きの遅れやぎこちなさが目立つと、周囲からの視線や期待に応えられないことへのプレッシャーを感じることもあります。これが運動への苦手意識をさらに強める悪循環を生んでしまうことも多いのです。
このように、DCDの子どもが運動でつまずくのは単なる不器用さ以上に、体の感覚処理や脳の情報統合の難しさ、そして心理的な負担が複雑に絡み合っているためです。この理解を深めることが適切な支援や環境づくりに繋がり、子どもが運動を楽しめるようになる第一歩となります。
3. おすすめの運動①:感覚を育てる「からだ遊び」

DCDの子どもにとって、まず大切なのは「できた!」という成功体験を積むことです。そのためには、競争を避けて自分のペースで体を動かせる運動が適しています。
特におすすめなのが、感覚を育てる「からだ遊び」です。遊びの中で自然と感覚統合が促され、苦手意識をやわらげることができます。
たとえば以下のような運動があります。
- トランポリン:上下運動で前庭感覚を刺激し、体幹も鍛えられるためバランス力向上に効果的です。
- 水泳:浮力で体への負担が軽く、ゆっくりとした全身運動が可能で、関節にやさしい運動です。
- ヨガ:ゆったりした呼吸とポーズで、自分の体の動きを意識しながらリラックスできます。
- バランスボール遊び:不安定なボールの上で遊ぶことでバランス感覚を養い、体幹の筋力も強化します。
これらの運動は、「正しく動くこと」よりも「楽しんで体を使うこと」が目的です。上手にできなくても安心してチャレンジできる環境が整えば、子どもは少しずつ「動くのが楽しい」と感じられるようになるでしょう。
親子で一緒に楽しんだり、個別の運動教室を利用したりするのもおすすめです。継続することで少しずつ運動スキルや自信が育まれていきます。
4. おすすめの運動②:ルールがシンプルで個人で楽しめるスポーツ
DCDの子どもが集団スポーツで苦手意識を持ちやすいのは、ルールが複雑で、即時の判断や仲間との協力が求められることが多いためであることが考えられます。そうした環境ではミスが目立ち、自信をなくしてしまうことも少なくありません。
そこでおすすめしたいのが、ルールがシンプルで個人でも楽しめる運動です。自分のペースで楽しみながら続けやすいのが特徴です。
以下のようなスポーツが向いています。
- 卓球:動きが単純で反復練習がしやすく、ラリーのテンポも自分で調整できるため負担が少ないです。
- ダンス:音楽に合わせて自由に動け、失敗が目立ちにくく表現の楽しさを味わえます。自分らしく動けるのも魅力です。
- ウォーキング:景色を楽しみながら気軽に続けられ、運動への抵抗感をやわらげる効果があります。
- ボルダリング:一人で集中して取り組める達成感があり、体幹やバランス感覚も自然に育ちます。
どの運動も大切なのは「成功体験の積み重ね」と「他人との比較を避けること」です。できることから少しずつ始めて、「今日はこれができたね」と具体的にほめることで、自己肯定感が育まれます。
また、本人の好みや特性に合わせて選ぶことで、より長く楽しく継続できる運動になるでしょう。
5. 関わり方の工夫〜「苦手」を受け止めて「得意」へつなぐ〜

発達性運動協調障害(DCD)のある子どもにとって、運動やスポーツはつらい経験や恥ずかしさを感じやすい場面です。そんなときに大切なのは、大人が子どもの気持ちに寄り添い、「うまくできなくても大丈夫」と受け止めることです。
安心して体を動かせる環境が、苦手意識をやわらげる第一歩になります。
できない動作に対して「どうしてできないの?」と責めるのではなく、「難しかったね」「少しずつやろう」と共感の声かけが子どもを励まします。失敗を重ねる中で、「今日は昨日より長く跳べたね」など小さな成長を言葉にすることが自信につながります。
また、子どもが何に不安を感じ、どんなサポートがあると安心できるかを観察しながら、無理のないステップで関わることも大切です。一度に多くを求めず、本人のペースに合わせて少しずつ取り組む姿勢が継続のカギとなります。
周囲が焦らず見守り、「やってみよう」という気持ちを大切にすることで、苦手だった運動が「ちょっと好きかも」に変わることもあります。その積み重ねが、やがて「得意」につながります。
運動教室やスポーツクラブに通う場合は、発達の特性を理解した指導者がいる場所を選びましょう。家庭でも失敗を責めず「やってみたこと」をほめる文化を作ると、子どもの自己肯定感が育ちやすくなります。
苦手を責めず、できる方法を一緒に探すことが、運動が「安心できる楽しい時間」になる土台です。
まとめ
発達性運動協調障害(DCD)は見た目以上に複雑な特性があり、本人や周囲の理解と工夫がとても大切です。焦らず寄り添いながら、少しずつ自信を育てることが運動の楽しさにつながります。
あなたも、子どもが安心して動ける環境づくりを心がけてみませんか?
あとがき
運動が苦手なことで、体育の授業で笑われてしまうこともあるかもしれません。でも、「周りと同じようにできないから変」という見方ではなく、一緒に「どうしたらできるか」を考え、サポートし合う社会であってほしいと願っています。
誰もが自分らしく安心して挑戦できる環境づくりを、みんなで力を合わせて進めていきましょう。
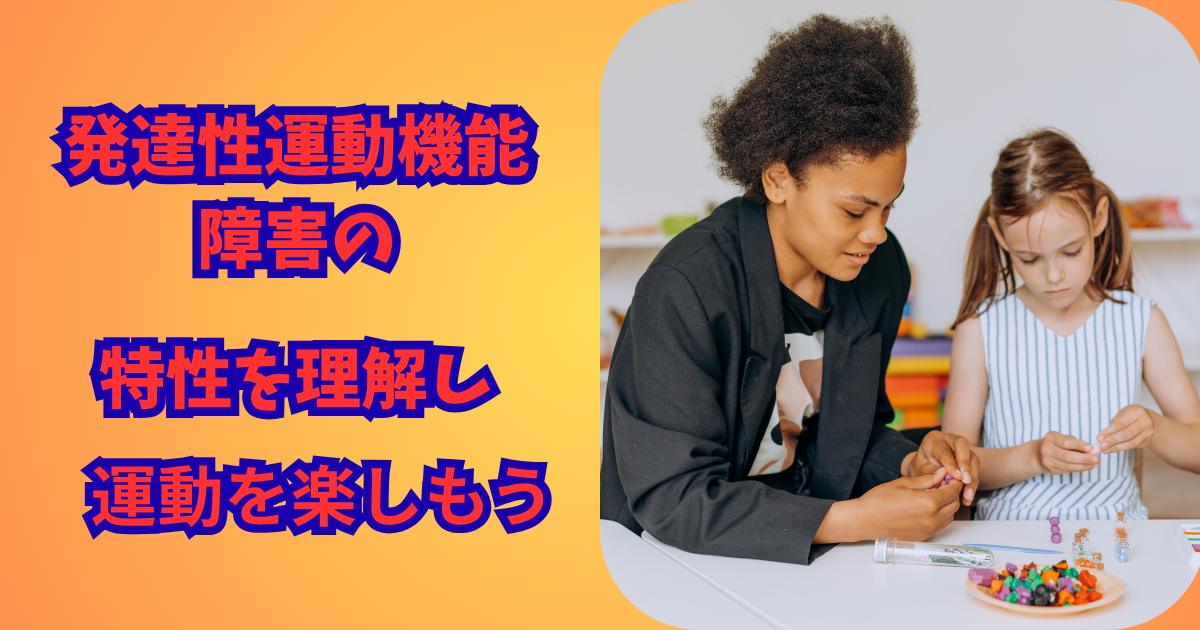

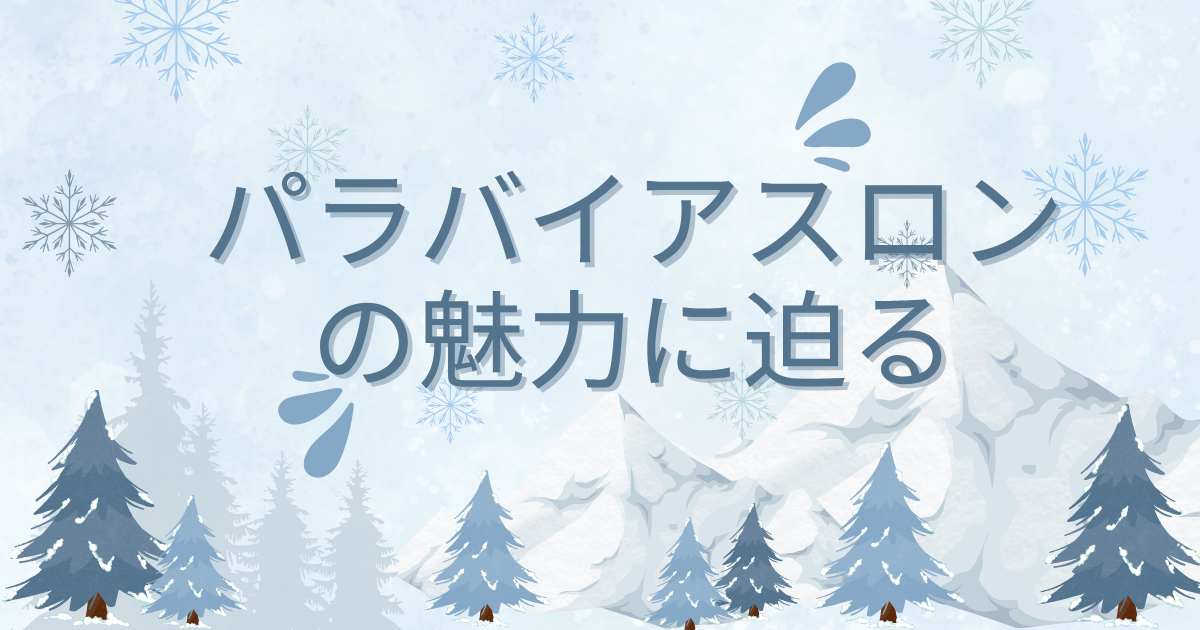
コメント