静かな集中の中で放たれる1本の矢。その行方にすべてをかける競技、それがアーチェリーです。パラスポーツとしてのアーチェリーも、オリンピックと同様の緊張感と駆け引きに満ちています。この記事では、パラアーチェリーの基本ルールや特徴、どんな選手がどのように競技を行っているのかを紹介します。「理解」から始めるパラスポーツの世界、のぞいてみませんか?
1. アーチェリーってどんな競技?静けさの中の真剣勝負
アーチェリーは、弓を使って矢を的に放ち、中心に近いほど高得点となる採点競技です。的は10点満点の円形で構成され、弓の種類や大会の形式によって、射つ距離や条件が異なります。たとえば、オリンピックではリカーブ弓を用い、70メートル先の的を狙います。
一方、パラアーチェリーでは、選手一人ひとりの身体状況に合わせて距離や的の大きさが調整されます。50メートル先の大型の的を使用するクラスもあれば、小さな的に高精度で挑戦するクラスも存在し、それぞれが異なる難しさと戦略性を持っています。
アーチェリーでは、わずかな風の変化や体のブレが得点に大きく影響します。そのため、選手は精度を高めるために、呼吸、姿勢、筋力の安定、集中力の持続といった要素を日々鍛え続けています。
パラアーチェリーにおける工夫と個性
パラスポーツとしてのアーチェリーも、基本的なルールは変わりませんが、選手の身体能力や特性に応じてさまざまな補助具や工夫が取り入れられています。たとえば、車いすに座った状態で安定したフォームを取る選手や、腕の自由が制限されている選手が口で弓弦を引いて矢を放つスタイルも見られます。
こうした補助具や姿勢の工夫は、単なるサポートにとどまらず、選手の能力を最大限に引き出すための重要な要素です。パラアーチェリーは、選手一人ひとりが自分の身体に合わせて最適なスタイルを築き上げていく、非常に個性的で戦略的な競技でもあります。
静けさが生む緊張感と魅力
アーチェリーの最大の魅力のひとつは、その静寂の中にあります。矢を放つまでの一連の動きには、息を整え、心を静め、集中を極限まで高める精神的なコントロールが求められます。選手が矢を放つ瞬間まで張り詰めた空気が続き、その静けさが逆に観客の緊張感を高めます。
的に矢が命中したときに響く「トンッ」という音は、試合の一瞬を強く印象づけ、観る者に深い余韻を残します。このように、アーチェリーは派手な動きは少ないものの、集中力と緻密な技術がぶつかり合う、極めて奥深い競技なのです。
2. どう違う?パラアーチェリーのルールとクラス分け

パラアーチェリーの試合は、障がいの内容や程度によってクラス分けされ、公平に競えるようになっています。大まかには「リカーブ」「コンパウンド」という2種類の弓を使った種目に分かれており、選手はそれぞれに適した種目で戦います。
リカーブはシンプルな構造で、オリンピックでも使われる伝統的な弓。コンパウンドは滑車を使った弓で、より少ない力で引けるのが特徴です。
パラアーチェリーの主な分類
パラアーチェリーでは、選手の障がいの程度や種類によって、いくつかのクラスに分かれています。それぞれのクラスは競技のルールや方法が少し異なり、選手が公平に戦えるように工夫されています。
- W1クラス:車椅子を使用する四肢麻痺(頸髄損傷)や、それに相当する障がいを持つ選手が対象。体幹の機能が効かない選手も含まれます。
- W2クラス:車椅子を使用する対麻痺(胸髄・腰髄損傷)や、それに相当する障がいを持つ選手が対象。
- STクラス:立った状態または座った状態で競技する選手による区分。
クラスごとに競技距離や的の大きさも異なります。
W1オープンとコンパウンドオープンは50メートル、リカーブオープンは70メートルの距離から矢を放ちます。
的の直径はW1オープンが80cm、リカーブオープンが122cm、コンパウンドオープンは48cm。中心を狙い、何本もの矢を放って得点を競います。
制限時間内に放つスピードや集中力の維持も重要な要素となるため、試合中の駆け引きにも注目です。ルールを知っていくと、「どのような工夫で的に当てているのか?」という見方ができるようになり、観戦もグッと楽しくなってくるでしょう。
3. 選手を支える道具とチームの力
パラアーチェリーでは、選手が自分の能力を最大限に発揮できるよう、使用する道具にも多くの工夫が凝らされています。
たとえば、手の力が弱い選手のためには、矢を口や顎で引く「マウスタブ」という装置があります。また、安定した射撃姿勢を保つために、特別な固定装置が取り付けられた車いすを使用する選手もいます。
こうした用具は、選手一人ひとりの体の状態や動き方に合わせて細かく調整されるため、まさに“オーダーメイド”の世界です。
さらに、選手をサポートするチームの存在も欠かせません。大会では、用具の管理や移動のサポートを行う補助スタッフが選手と連携して行動します。
とくに屋外競技では風の影響も大きく、風速を読む技術やタイミングを見極めるアドバイスも重要になります。また、選手が精神的に落ち着いて競技に集中できるよう、メンタル面での支援をするスタッフがいることもあります。
こうしたサポートを受けながら、選手は自分自身のリズムを保ち、集中力を高めていきます。パラアーチェリーの魅力は、選手の技術や努力だけでなく、それを支える多くの人たちとのチームワークにもあるのです。
選手とサポートスタッフの間にある信頼関係こそが、確かな一射を生み出す大きな力になっているのです。
4. 見て楽しむ!観戦のポイント

パラアーチェリーは、静かな環境で行われる競技のため、観戦にも独特の楽しみ方があります。
まず注目してほしいのは、選手が矢を放つまでの一連の動作。呼吸を整え、弓を引き、そして放つ。その動作ひとつひとつに意味があり、選手の集中が伝わってきます。
試合では得点の表示もあるので、どの選手がどれだけの精度で的を狙っているのかが一目でわかるのも魅力です。
観戦のポイント
ここでは、パラアーチェリーをより楽しむための注目ポイントをいくつかご紹介します。
- 射つまでの所作:選手ごとにリズムや動作が違うので、見比べてみると興味深い発見があるかも。
- 矢が的に当たる音:「トンッ」という軽快な音が、観戦の臨場感を高めてくれるでしょう。
- 点数の推移:リアルタイムで表示される得点から、勝敗の駆け引きがわかりやすい!
また、「どんな工夫で矢を放っているのか?」を知って観戦すると、より深い理解が得られます。ただ見るだけでなく、選手の工夫やチームの連携を想像しながら見ると、ぐっと面白く感じられるはずです。
初めての人でも楽しめるよう工夫された競技なので、ぜひ一度映像などで観戦してみてください。
5. 学校でどう活かせる?教育現場との相性
パラアーチェリーは、学校教育の中でも活用しやすい題材です。
たとえば総合学習や道徳の授業で、「自分に合った方法でチャレンジすること」「多様性を理解すること」などのテーマにぴったりです。
また、体育やキャリア教育とも結びつけることができるでしょう。実際に映像を見せる、体験会を行うなどすれば、生徒たちの関心も高まるでしょう。
競技用の道具に工夫があることや、障がいのある選手がどのように目標を達成しているのかを知ることで、視野がぐっと広がります。
重要なのは、「すごいね」「かわいそう」といった表面的な感想に偏らず、スポーツとしての面白さをきちんと伝えること。パラアーチェリーの世界には、選手の工夫やチームの協力、技術の高さなど、学びにつながる要素がたくさん詰まっています。
たとえば、どんな方法で的に当てているのか、どうやって集中力を保っているのかといった観点からも、深い気づきが得られるはずです。
生徒たちにとって「障がい者スポーツ=特別」ではなく、「自分たちと同じスポーツのひとつ」として自然に受け入れられるような伝え方が大切です。
そのうえで、自分とは違う環境にいる人の工夫や努力に目を向け、思いやりや尊重の気持ちを育てるきっかけにもつながるでしょう。
6. まとめ

パラアーチェリーを知ることは、スポーツの奥深さだけでなく、人がもつ可能性や工夫の力を知ることにもつながります。
静かな空間に広がる緊張感、そしてその中にある挑戦と工夫。少しでも興味を持ったなら、映像を見たり大会に足を運んだりして、実際の競技にふれてみてください。新しい視点がきっと見つかるはずです。
7. あとがき
この記事を書こうと思ったきっかけは、2024年のパラリンピックで初めてパラアーチェリーを観たことでした。
静けさの中で放たれる矢に込められた集中力や技術、そして選手それぞれが工夫を重ねて挑戦している姿に感動し、「もっと知りたい」と強く思いました。調べていく中で、スポーツとしての奥深さやチームの支え、多様な工夫に触れることができました。
この記事が、皆さんがパラスポーツに興味を持つきっかけになればうれしいです。


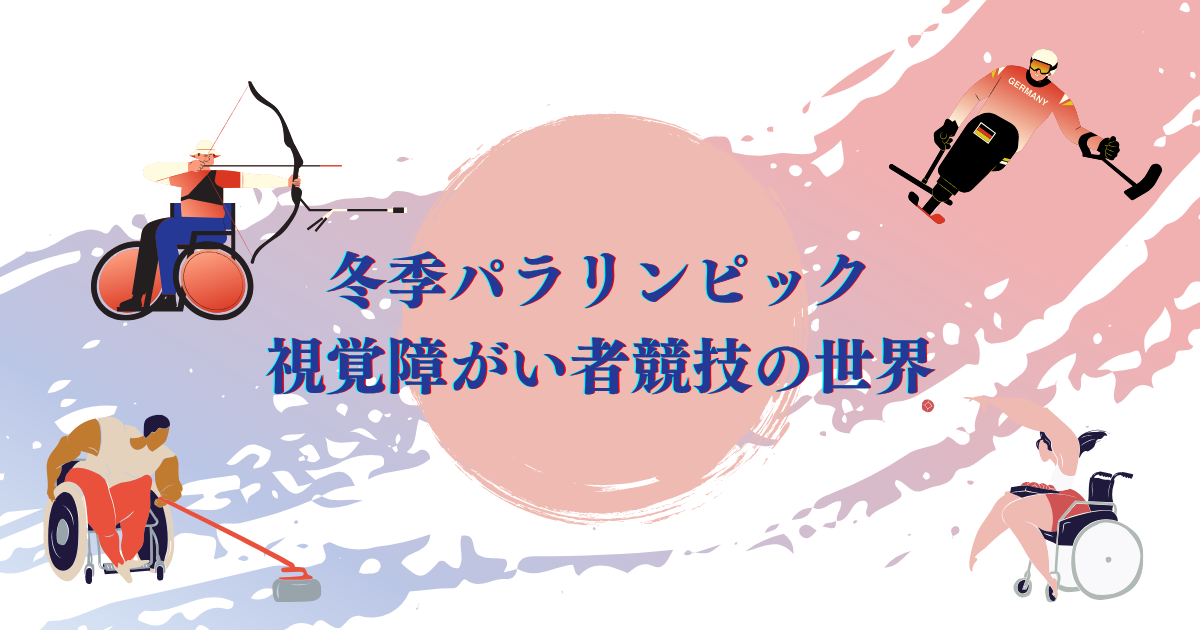
コメント