サッカー元日本代表の中村俊輔選手は、繊細なボールタッチと創造性あふれるプレーで多くの人々を魅了しました。しかし、彼がキャリアの中で大きな試練を経験したのは、2002年の日韓ワールドカップのメンバーから外された時と言えるでしょう。本記事ではそんな苦悩を乗り越えたアイテムの一つかもしれない、彼が実践してきたサッカーノートの秘密に迫ります。
1. 挫折が生んだ成長の習慣
2002年に日本と韓国で共同開催されたワールドカップは、日本中を熱狂の渦に巻き込みました。
しかし、当時、日本代表の中心選手の一人であった中村俊輔選手は、この晴れ舞台のメンバーから外れるという経験をしました。
代表に落選したことについて、2021年12月18日に公開されたYouTube動画では「全く悔いはない」と話しましたが、その心境は複雑だったようです。実際、ワールドカップ期間中、日本代表の試合は観戦しなかったといいます。
彼の才能を疑う人は少なかったものの、世界の舞台で戦うには、何かが足りないと判断されたのかもしれません。
この苦い経験が、彼のその後の人生を大きく変えるターニングポイントの1つと言われています。
1-1. 日韓W杯落選という大きな壁
日韓ワールドカップのメンバーから外れたことは、中村俊輔選手にとって、単なる挫折ではなかったようです。この期間、彼はただ落ち込んでいるだけではありませんでした。
心の中で湧き上がる複雑な感情や、漠然とした不安をどうにか整理しようと試みたようです。
1-2. どん底から見つけた新たな光
ノートを書くことで、中村俊輔選手は落ち込んだ気持ちをコントロールし、納得のいくプレーをイメージしてきました。また、サッカーノートを使って課題を明確にし、それを克服することで目標を達成してきたのです。
このノートのきっかけを生んだのは、桐光学園高校2年生の時にありました。サッカー部でメンタルトレーニングを指導していた豊田一成先生から、試合に勝つために、強い気持ちをコントロールする方法の一つとして勧められたことでした。
それ以来、彼は日々の練習や試合での気づき、そして自分の感情を記録するサッカーノートをつけ続けてきました。
この習慣は、彼が自分自身の心と向き合い、客観的に自己分析を行うための重要なツールとなりました。
ノートに書くことで、自分の思考が整理され、何が課題で、何を改善すべきかが明確になっていったと考えられます。
2. サッカーノートはただの日記ではない

中村俊輔選手がつけていたサッカーノートは、単に練習メニューを記録するものではありませんでした。それは、彼自身の内面と深く向き合うためのジャーナリングと呼ばれる、思考の整理術でもあったと考えられます。
ジャーナリングとは、頭に浮かんだことをありのままノートに書き出す習慣です。日記のように出来事や感情を掘り下げるだけでなく、思考を止めずに自由に書き連ねるスタイルもあり、目的や気分に合わせて取り組めるのが特徴です。
ノートを書き続けることで、彼は自分の強みや弱みを客観的に見つめ直すことができたようです。
なぜあのパスは通らなかったのか、なぜあのプレーはうまくいったのか、といった疑問を文字にすることで、感情に左右されない冷静な分析が可能になったと言えるかもしれません。
この習慣が、彼のプレースタイルをさらに進化させる土台となったと考えられます。
2-1. 感情を言語化するジャーナリング
彼はノートに、悔しさや不安、自分の弱点、誰にも言えないこと、サッカーに対する考え方、様々な心の動きを書き留めています。
感情を言語化することは、心理学的な観点からも非常に有効な方法です。
モヤモヤとした感情を言葉にすることで、その感情の正体を突き止め、原因を探るのに役立つかもしれません。これにより、彼は感情に振り回されることなく、冷静に次の行動を考えることができるようになったのでしょう。
このように、サッカーノートは、単なる技術的な記録を超えて、彼のメンタルを鍛えるための重要な役割を果たしていたと考えられます。
それは、どんな困難な状況でも、自分の心をコントロールし、常に最高のパフォーマンスを発揮するための、彼なりのトレーニング方法だったと言えるでしょう。
2-2. 課題を明確にする思考のツール
さらに、ノートは彼が課題を明確にするためのツールでもありました。彼がサッカーノートで大切にしていたのは、自分を過大評価しないという姿勢です。
中学3年生の時、驕りからレギュラーの座を年下の選手に奪われた経験があったからです。
同じ失敗を繰り返さないため、そしてプロサッカー選手として向上心を失わないためにも、自分への評価は厳しく、常に課題を中心にノートを書いていました。
今に満足したらそこで成長は止まってしまう、という強い思いがあったのかもしれません。
目標が明確になることで、毎日の練習に意味が生まれ、モチベーションの維持にもつながったと考えられます。このようにサッカーノートは、彼の思考を可視化し、成長するための道筋を照らす役割を担っていたのかもしれません。
3. ノートが導いたキャリアの転換期

日韓ワールドカップの落選後、中村俊輔選手はイタリアのレッジーナに移籍しました。当時、日本人がセリエAで活躍するのは非常に難しいと言われており、彼もまた、異国での適応の難しさに苦しむ日がありました。
試合に出られない日々が続く中で、中村選手は自らを厳しく見つめました。2004年に所属していたイタリアのレッジーナで出場機会に恵まれなかった際、彼はサッカーノートにこう記したそうです。
「試合に出られないのは、自分の力が足りないからだ。ふてくされたり落ち込んだりしている暇があるなら、自分に何が足りないのかを考え練習し、監督にアピールして結果を出す。努力を怠るな」
この時期は、彼が最もメンタルに関する言葉をノートに書き綴った時期だと言われています。過去の経験も乗り越えるヒントになっていました。
2001年に病気で一時戦線離脱していた時期に、何を考え、どう過ごしていたかを振り返ることで、目の前にある困難をどう乗り越えるか、その道筋を見つけていったのです。
中村選手は、行き詰まった時ほど、このノートを見返すと言います。このノートが、異国の地での孤独や葛藤を乗り越え、自分のサッカーを確立するための支えになったと言えるでしょう。
4. サッカーノートを続けるためのヒント
中村俊輔選手の例からわかるように、ノートに書き出すことはアスリートだけでなく、私たち自身の成長にとっても非常に有効なツールかもしれません。ここでは、彼に習って、書き続けるためのヒントをいくつかご紹介します。
4-1. 完璧を求めない書き方
ノートに書く内容は、何でも構いません。今日嬉しかったこと、失敗してしまったこと、その失敗の原因と対策、将来の目標といったことでも良いでしょう。
文章の上手い下手を気にする必要はありません。大切なのは、自分の心をありのままに書き出すことです。感情や思考をそのまま文字にすることで、新たな気づきや発見が生まれるかもしれません。
また、ノートは一冊にこだわらず、気分に合わせて変えてみるのも良いかもしれません。好きな表紙や、書きやすい紙質のノートを選ぶことで、書くこと自体が楽しくなることもあるでしょう。
書くことを習慣にするための、ちょっとした工夫をしてみることをおすすめします。
4-2. 継続するためのコツ
ノートと向き合う時間を決めておくことも、習慣化には有効かもしれません。また、書いた内容を後から見返してみることも大切です。
過去の自分の思考や感情を振り返ることで、どれだけ成長できたか、何が課題だったのかが客観的にわかります。
過去の自分を褒めてあげることで、今後のモチベーションにもつながるでしょう。このように、ノートは未来を切り開くためのツールにもなるのです。
5. まとめ:挫折は成長のチャンス

中村俊輔選手が高校2年生から続けてきた「サッカーノート」という習慣は、単なる記録を超えて、彼の人生を豊かにする上で非常に有効なツールだったと言えるかもしれません。
彼はノートを通じて、自分の感情や思考を整理し、課題を明確にすることで、世界でも有名な日本のトッププレーヤーの一人へと成長していったのです。
中村俊輔選手の例が示すように、彼のサッカーノートは、自身の心を整え、自己成長を促すうえで大きな力になると言えるでしょう。
あとがき
挫折を経験した時、あるいは漠然とした不安を感じた時、ぜひノートを手に取ってみてください。
あなたの心の中にある答えが、きっと見つかるかもしれません。小さな習慣からでも、未来は変えられる。中村俊輔選手のサッカーノートは、私たちにそう教えてくれているのではないでしょうか。

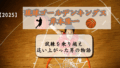
コメント